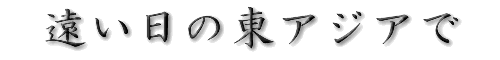
|
はじめに
私は青年の頃、両親弟妹達とともに朝鮮に住んでいた。父は大規模な鉱山会社の技術社員で、昭和十年(一九三五年)に朝鮮の事業所に赴任して以来、家族を京城(現在のソウル)に住まわせ北朝鮮地区に点在する鉱山に勤務した。 この物語りは昭和十二年(一九三七年)の夏から昭和十七年(一九四二年)の初頭にわたる私の朝鮮での生活体験にもとづいた自分史的記述である。この五年余りの期間は、私にとって京城帝国大学の予科から学部の第三年次にわたる学生生活の頃であり、日支事変の勃発からその長期化、そして太平洋戦争に突入した当初の頃までの期間でもある。 明治四十三年(一九一〇年)、日本は大韓帝国にたいする外交、軍事両面からの威圧と強要によって日韓併合条約を締結し、朝鮮全土を日本領土とするとともにその国民である朝鮮民族のすべてを日本帝国の臣民(国民)と定めた。それ以後、日本内地からの移住或いは就職、転勤等によって朝鮮に在住する内地人の人口は漸次増加し、また深刻な事情を踏まえながらも、朝鮮民族の内地への人口移動も年を追って増加の一途を辿った。 この物語りは、合併後三十年余りを経た時期における私の生活体験、そしてそれを通して内地人の生活や朝鮮の人々との交流を描いたものである。そしてそれらを素材とした内地人、朝鮮人相互間の日常的な生活意識、生活心理に、民族問題がどのように反映していたか、どのように浸透していたかを一貫したテーマとしてとりまとめようと心がけたのである。 記述が昭和十七年(一九四二年)初頭頃までとなっているのは、私自身が戦時繰上げ卒業として、昭和十七年九月に大学を卒業し引続き陸軍部隊に入営したためである。私は入営後第二次大戦が終る(一九四五年)までの間は兵営とフィリピンの戦場で過ごす境遇に置かれていた。したがって私は終戦にいたる数年間そして引き揚げの頃の朝鮮での市民生活を体験していない。日本が朝鮮を領有していた最終段階のこの数年間に、朝鮮民族にたいする日本の政策や処遇について、現在もなお格別に採り上げられている諸問題がある。それは「工場、炭鉱への労働者の強制連行」「兵役に服させるための徴兵制の施行」そして「従軍慰安婦」の問題である。 これらの問題は日本が米英と戦争を開始した当時の急速な戦備拡張の過程、そして戦勢が敗戦の淵に向かって傾斜して行く過程で顕著となったことがらである。日本国民を構成する民族としてのたてまえを根拠として、日本と運命を共にすることの不本意な朝鮮民族にたいし、国家が強制的に、そして結果的には敗戦の道連れにしようとした現象の一環とも見られるものである。 いずれにしても日本国家が朝鮮民族を保護国、領有国として対処して来た明治末期以降の四十余年の過程は、国家としても、また国民としても深い反省を重ねて行かなければならない歴史的事実である。 日本は明治三十八年(一九〇五年)日露戦争に勝利し、ロシア帝国の満州における清国にたいする諸権益を継承し、その国勢を駆って、強圧外交によって日韓併合条約を締結し、明治四十三年(一九一〇年)韓帝国の国土国民を日本帝国の領土国民と定めた。このことは欧米諸国によるアジア植民地化にたいする防衛に主眼を置く日本の「アジアの道」を、日本を指導国家とした東アジア地域の国家、諸民族の共栄を標榜する「アジアの道」へと変容さすに至った。第一次大戦を経て日本の国際的地位は、英国、米国に次ぐと言われる程に向上した。そしてソ連に対する国防上のたてまえを前面に置いて、日本は東アジアにおける国勢の優位性を一層強化しようと企て、昭和七年(一九三二年)以降は、満州に駐留する関東軍の威力を背景に、アジアの五民族の協和による満州国を建設した。以後、国際連盟加盟国や米国の反対と批判を顧慮せず、唯ひたすらに日本はアジアの指導国家として自認する道を歩み続けた。 朝鮮民族は日韓併合の初期から二十年間余りは、日本国民ではあっても被領有民族として区別され、区別されている範囲でその民族的独自性が発揮されていたとも言うことができる。このことは明治四十三年の日韓併合当時においても、またそれから十年を経た大正九年(一九一八年)の万歳事件として記録される独立要求行動当時においても、日本の諸新聞のニュース或いは論調に明らかに見受けられる事柄である。そこには朝鮮民族の民族性に対すを配慮の上に日朝両民族の融和の重要性が強調されている。 しかし日本が東アジアの指導国家としての道を策定し、日本国民がアジアの指導民族であるとの選民的指導理念を掲げるに至って、同じ日本国民を構成する朝鮮民族にたいしても、その民族の独自性を否認して日本民族化する方向へと民族政策を改変した。所謂朝鮮民族にたいする皇民化政策である。内鮮一体の理念の内容が朝鮮民族の皇民化に変容し、日本語使用の強制、創氏改名の促進等の諸政策はその具体化であった。 当時朝鮮で生活していた内地人の一人として、朝鮮民族の友人や知人と接するときに、その人々の被領有民族としての精神的苦痛を推測して語る言葉に窮する場合も多かった。また積極的にそれらの政策を肯定して順応しようとする人々にたいしては、どのようにその心情を認識し協力すれば良いのか、深甚の配慮も必要だった。 私にとって、私の青春を育んだ朝鮮半島全体が第二のふるさとである。青空の空の青さが、一つにまとまった朝鮮の象徴である。もとより晴天ばかりが続いていたのではない。しかし私の印象に浮かぶ風光には常に青空が冴えわたっている。南山の緑、北岳の岩峰、漢江の流れ、その美しい自然に抱かれた京城の街々は青空の下に拡がっていた。慶州の古都も、金剛山の景勝も、蓋馬高原も、平壌の牡丹台もそして鴨緑江の水も、今思い出して目に浮かぶ景色はすべて紺碧の空の下にあった。 合併後の三十年余を経た昭和十年代の段階で、私はこの青空の下の朝鮮の大地を日本の国土として意識し、この地で生活した。そして疑心と錯誤を重ねながらも、朝鮮民族が近い将来に日本民族と同等の立場で、実質的にも日本国民として団結できる日のあることを心の底で期待していた。一般に朝鮮に住んでいた内地人の多くは、この考えの方向に一致点を見出していたものと思う。 しかしこのような思考を基本とする限り、内地人側がいかに人間性豊かに良心的に朝鮮の人々に接しようとしても、それは所詮、同情の域を越え得ないものであり、相手側から親愛の情を受けることがあっても、民族の苦悩の真の理解者として信頼されることは難しいことだった。民族の独立を諦めて、積極的に日本国家の国民として、実質的に日本民族と対等な地位を確立するという路線を信条として進む人々も少なくはなかった。しかし内鮮一体という日本の国策が、最終的に朝鮮民族の民族性を変革し皇民化するという方向を強制したために、この路線を信条とする人々の期待を失わしめるに至ったのも事実である。 日本がカイロ宣言、ポツダム宣言を受諾して第二次大戦が終り、朝鮮民族は独立を回復した。しかし日本民族と朝鮮民族とが、国家と国家との関係として国際情勢や諸政策に影響され易い今日に在っても、隣合った国土における長い年月のしがらみに結びついた両民族は、底深い運命の流れを共にしていることもまた否定し得ない。 |