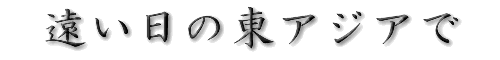
|
第一章 京城の街で
軍隊輸送列車が巨大な蒸気機関車に牽引されて、京城駅のはずれの七番ホームに重々しく入り込んで来た。 昭和十二年(一九三七年)八月も半ばの午後二時三十分、これで午後になってから二本目の軍用列車である。十数輌の客車には開戦して間もない中国戦線に向かう部隊が搭乗しており、日焼けした顔を窓々から覗かせていた。ホームでは列車が停車し始める頃から、数百名の日本人(内地人)たちが手に手に日の丸の旗を振りながら、万歳、万歳と歓呼の声をあげていた。京城在住の国防婦人会員を中心に、市内の各町会から通過部隊を歓送するために割り当てられて集まった人たちである。列車が停車している二十分余りの間に、湯茶や氷水で接待し、或いはまとまって兵隊たちと軍歌を斉唱している光景もあった。 当時十七歳の私もその歓送者の一人だった。京城の市民として親弟妹たちと暮らす私は、京城大学予科に在学する学生だったが、たまたま夏期休暇中でもあり、母がお盆で郊外の墓地に祖母の墓参りに行くので、私が代わって歓送に参加していたのである。父は鉱山会社の技術社員として朝鮮北部の鉱山に赴任しており平常は自宅に居なかったので、長男の私は今回に限らずしばしば世帯を代表して町内の会合にも出席した。駅頭に通過部隊を見送る行事に参加するのも夏に弱い母親に代わって既に数回に及んでいた。
事変勃発当時、日本の華北駐留軍は四千名だった。中国との条約で決められていたこれだけの兵力で数十万の蒋介石軍と戦争を続けることはもとより無理だった。結果的に言って停戦交渉は日本の兵力を応急に増強する時間を確保するためにも必要だった。七月には急遽満州の関東軍二個旅団および朝鮮京城の第二十師団が派遣された。続いて八月には日本本土から熊本の第五師団、広島の第六師団、姫路の第十師団の派遣が決定された。八月上旬から連日のように京城駅を通過していった軍用列車は、主としてこの内地からの派遣部隊を北支に急送するための列車だった。そしてその多くの軍用列車を編成運行するために、七月下旬から八月中旬までの間は、釜山から京城、平壌、安東、奉天へと朝鮮、満州を結んで続く日本の大陸輸送幹線は、一般旅行客用の列車ダイヤが平常の三分の一に減らされていた。 昭和十二年当時の京城の人口は接続都市を含めると八十万余りに達し、そのうち内地人は二十万名を超えていた。京城は李氏朝鮮以来の五百年にわたる首都であり、日韓合邦から三十年近くたって、朝鮮における行政、経済、教育、交通の中枢近代都市として発展していた。そして北に隣する満州国の発展は、京城を日本の国勢を大陸に拡張する基地的機能を担う都市としての様相も備えさせていた。 軍用列車の歓送は私にとって五回目であり、一日に二本の列車を送ることもあって八本日の歓送だった。いずれも停車時間が二十分前後あったので、その問に湯茶や氷水の接待や軍歌の斉唱等が行われ歓送の盛り上がりもあったが、何といっても通過部隊の見送りは回数が重なると演出的な行事のようなマンネリ化も否めなかった。また輸送途中の兵隊たちには長い列車の旅で疲労の様子がありありと見受けられた。内地の部隊所在地から列車と船と列車で既に二十四時間以上はたっていたであろう。そしてこれから北京や天津の先の戦場まで更に一千六百キロメートル以上を列車に揺られなければならないのである。 歓送者には男性が少なかった。官庁や会社に勤務し或いは商店や工場等も営業中の真昼の時間だから当然である。また朝鮮籍の市民には歓送の割り当てはないようだった。したがってプラットホームに並ぶ歓送者は殆ど内地人の二十代から五十代位までの婦人たちだった。事変当初は歓送の際に歌う歌も少なかった。ましてや婦人たちとともに斉唱できる歌はなお少なかったのである。「天に代りて不義をうつ」に始まる「日本陸軍」という歌や、「ここはお国を何百里」で始まる「戦友」、或いは「万朶の桜か襟の色」で始まる「歩兵の本領」等が主に繰り返し歌われた。 しかし「……離れて遠き満州の 赤い夕日に照らされて……」と歌っているうちに、声を大きくすればする程勇壮感よりは悲愴感がただよい、「戦いすんで日が暮れて、さがしにもどる心では」と歌ってくると歓送者たち自身がついしんみりした気分になってしまうのだった。列車の窓からこれに和して歌っている兵隊たちもなんとなく疲れておつき合いに歌っているという表情だった。駅のはずれのプラットホームには屋根のない部分が全長の半分ぐらいあり、そのあたりには午後の夏の陽射しがぎらぎらと降りそそいでいた。その後この「戦友」という歌は、歌詞の感傷性が理由で部隊の歓送には歌われなくなった。 長途の列車輸送に疲れ気味の兵隊たち、割り当てられた歓送任務を果たすために通過部隊に歌と声援を送る市民たち。そして歓呼の声の途切れた絶え間のホームを包む真昼の静寂。私はこのたまゆらの静寂の中に、今始まったばかりの中国との事変の行方を、戦争の現実と平和への幻想との錯綜した思いで噛みしめていた。
「どこに行って来たんか」と井上は私に問いかけた。「町内会の割り当てで、通過部隊の歓送だ」「俺のところは親父も勤務校が休暇だし、お袋と交替で参加しているらしい」と井上は言って、「通過部隊の見送りをしてどんな気持ちになる?」と聞いた。「何回も見送っているうちに、通過部隊全体の歓送ではあっても、窓から顔を出した兵隊と眠が合ったり、声をかけたり、一言でも語り合ったりすると、その一人一人の家族との別れや恋人との別れの心情が思いやられて、つい身につまされてしまうんだ」と私はその情景を目に浮かべながら感情を込めて言った。井上は手にした文庫本を示しながら、「今丁度一冊目を読み終えたところだ。休暇中に四巻全部を読んでしまう積りだが、この『戦争と平和』の一冊目のところに、主人公のアンドレイが平和の日々と決別して、祖国ロシア帝国のためにナポレオン軍との戦争に出征する当日の家族との別れの情景や、戦闘で重傷を負って、薄らぐ意識の中に去来する幻想等が掘り下げて描写されている。戦争の始まったこの頃の自分の気分もあって、今日も未だその感銘深い余韻が続いている」と告げるように語った。 こんな話をしながら二人は東大門行きの電車に乗り明治町で降りて、学生の行きつけの茶房「白龍」に立ち寄った。 そこには学友の具本純が上級生の朝鮮籍の学生と二人で語り合っていた。 「今日は団成社(映画館)で『商船テナシティ』の再映を観て来た。今あと味を楽しんでいるところだ」と具本純は言った。 「そうか、何日まで上映している? 俺も見ておきたいな」と私は言った。井上は、 その本の表題を見やりながら具本純は、「とうとう戦争になってしまったなあ」と思いついたように言った。 「俺たちの人生には戦争がつきまとってゆくのかなあ」と私が言うと、井上は具本純に向かって、「あんたたちは兵役の義務が無いから日本の戦争を傍観者的に考えることができるだろうな」と語りかけた。 すると今まで黙っていた上級生の朝鮮籍学生が口を開いた。 「日本は明治以来武力で国を成長させて来たから、これからも戦争とはますます縁が深くなるよ。国民皆兵はあんたたち日本人にたいする国策だからな」 彼の言葉は私や井上に対し皮肉を言っているように聞こえたし、ニヒリスチックな態度で今度の戦争を非難しているようにも思えた。しかしこんな話を喫茶店内でしていると、私服の憲兵や特高ににらまれる可能性もあるので、私は話題を変えようとした。 「新協劇団の村山知義が『春香伝』を上演する準備を進めているのを知ってるか」 「新聞に載っていたんだが、演出の準備のために『春香伝』にゆかりのある土地の人々に接していろいろ話を聞いていると、自分も朝鮮の血を受け継いでいるような気持ちになると村山知義が語っていたそうだ」と井上が言うと、その言葉を受けて朝鮮籍の上級生が言った。 「内地から訪れるインテリたちは、朝鮮民族の文化や伝統に触れると、みんなが親しみを込めてこのような気持ちを言う。内地で見受ける朝鮮人の労働者や貧しい生活者からの印象と随分違うからだ。そして朝鮮民族の苦境に同情する。しかしそれだけだ。単なる一過性の同情に終ってしまう。民族の物質生活面にはこだわるが更にもっと深層の精神的苦痛までを本当に察しようとしない」
「今日は立神にさそわれて大学の弓道場に行き、的張りを手伝って来た」と江上が言った。 私は、「これは小説だが、シュトルムの『みずうみ』(インメンゼー)というのを文庫本で読み、翻訳の内容が美しいので、これを原文で読んでみようと始めたばかりだ。ドイツ語の初歩の段階には丁度向いていると思う」とうなずきながら言うと、立神は、「中村はロマンチストだからな」と答えながら、「この頃通過部隊の見送りに駅に行ってるそうだな、感激して旅行まで取り止めたそうだが」と問いかけた。 「俺は中国兵を憎めない。しかし戦闘が始まれば彼等も日本兵にたいして弾を撃って来るんだ。これが戦場だ。その戦場に向かって兵隊たちがどんどん送られて行くんだ。みんな生命の不安を懐きながら自分の任務として死を覚悟して戦線に向かって進んで行くんだ。輸送列車の窓ぎわにそのような兵隊たちと目が合ったり、手を握ったりすると、人間としての純粋な触れ合いを感じるんだ。いろんな執着を断念し、あきらめて戦場に向かっている生の人間たちとな」 と語り始めると、江上が、「戦争が始まっていることは、街の雰囲気では未だ殆ど感じられないからな」と言い、言葉を続けて、「人間同志、本来憎み合っているのではないけれど、戦場では敵味方同志が相手を殺さなければ自分が殺されるという危機感から弾を撃ち合っているんだものなあ」と深刻な口調で言った。 「今度の戦争は国家としても中国を敵としないと宣言し、事変として取り扱っている。戦争する意味をどう考えたらいいのかなあ」と井上が低い声でつぶやいたので、私は「そうだな、個人として考えればな」と同じように声を押さえて言った。 「しかし俺たちには国民としての立場、日本民族としての立場があるしな」と江上が言った。 この問題は折に触れて内地人の間でいろいろな形で問題になった。そして多くの内地人は、朝鮮民族の大多数の者は合邦による日本国民であることを喜んではいないし、また日本の国力が強いのでやむを得ず日本国民にされたままになっているのだと推測していた。それにしてもこの根源の民族問題を、私はクラスメートの朝鮮民族の学友から忌憚のない率直な見解として聞きたかったが、未だそこまで打ちとけた間柄になった友人はいなかった。 喫茶室での雑談はとりとめもなかったが、戦争が始まりその戦争が単なる局地的事変として短期で終結する期待も懐き得る昭和十二年の夏の段階だった。そして学生のわれわれにとって、戦争の経過も文学や哲学的思考の世界も、未だ日常的には並列した話題だった。しかし開始された日支事変という戦争は、私ども同じ地続きの大陸生活者にとって、個人の生活意識を越えて国民として日本民族としての自己を、自覚と反省上を含めて見つめざるを得ない状況へと押し進めていた。 他の友人たちと別れて、私は江上と本町三丁目から四丁目へと商店街を歩いて行った。私は江上とクラスは別だったが共に弓道部に入部していたし読書を通じて語り合うことが多かった。またお互いに近所の知り合いの女学生たちに閑しても青春の世界に登場するメッツェンとして話題に花を咲かせた。 「中村、この頃彼女はどうしている」「ああTさんか。彼女は俺に自分の読んだ日本文学の小説の感想を会うたびに語りかけて来るんで、こっちは未だ読んでいないものは大いそぎで一晩で読まなきゃあならなくなるし、いそがしいよ」これを聞いて江上は、「変わった形ののろけ話か」と言って笑った。夏の午後の四時は未だ夕日も暑い。私たちは杉の朴歯の下駄の音をたてながら、腰の手拭で汗を拭き拭きゆっくり歩いていた。 昭和十二年の頃は、総督府の朝鮮民族にたいする政策は、朝鮮民族が日本国民として日本民族と融和するようにとの懐柔政策がとられていた。朝鮮民族の学ぶ小学校(普通学校)では総督府発行の朝鮮語の教科書で民族語の授業も行われていたし、日常の生活において日本語も強制していなかった。他面在鮮の日本民族(内地人)にたいする政策として、朝鮮民族と融和するよう努力が要望されていた。即ち朝鮮籍の人を呼称する際には「朝鮮のひと」或いは半島人と呼称するようにとの具体的指導が行われ、領有以来の二十数年間に生じていた民族差別的な言葉や態度を改めるための内地人にたいする指導が、学校教育を通じ或いは新聞、ラジオ、町会組織等を通じて積極的に行われていたのである。 この年の四月、予科の入学式に出席した際に予科部長の中村寅松教授が式辞の冒頭で、「内地在籍の諸君並びに半島在籍の諸君、諸君はこのたびめでたく京城帝国大学予科に入学され……」と述べられ、朝鮮民族にたいする呼称を特に気遣っておられるのを知って、私は朝鮮における民族問題がこれまで想像していた以上に深刻であると感ぜざるを得なかった。どのように日本の国の経済力が向上し軍事力が強大となっても、東アジア大陸への発展という国策を遂行するには、朝鮮民族との融和が基本的な重要課題だった。国力の圧迫によらない民族間の真の融和を実現しようとしても、合併領有の経緯に始まりその後の二十年余の統治方式が原因のしこりが、朝鮮民族のこころに抜きさしならない怨念を植えつけてしまっていたのである。融和政策はとられていても、その政策は総督政治の対象である朝鮮半島の地域に対するものであり、内地在住の朝鮮籍を持つ数十万の労働者や貧困生活者を含めた日本全域にわたる日本政府の政策とはなっていなかった。 朝鮮民族の日本への反抗心は、大正八年三月一日の独立要求の統一行動が鎮圧されて以来、潜在的には意識的に普遍化しているように思われた。特に朝鮮や内地で高等教育を受けた朝鮮籍のインテリの殆どすべてが少なくとも胸の中に日本への反抗心を抱いていた。わたくしども内地在籍の学生は朝鮮在籍の学生と語り合う際にはお互いに政治問題、民族問題に触れる談話は心して避けるようにしていたし、学友としてうちとけて語り合う話題も、主として西欧の思想や文学そして映画等であった。私は学友の朱宰黄や金性会、そして具本純たちと授業の休憩時間にしばしばお互いの民族の文化や風習等について語り合ったが、政治的な話題に触れることは無かった。
私の一家はこの山麓の住宅街の一部である大和町に住んでいた。曹渓寺という鐘楼のある寺院が家の近くの丘の上に建っており、そのなだらかな丘陵は南山の山頂までゆるやかに続いていた。夕方の六時にはその凡鐘が深い音色を住宅街や商店街に湊ませていた。 市街の中央部の南山麓の突出した台地にはカソリック教会の大伽藍が聳えていた。たそがれどきの七時には、近代的なビルが林立し典雅ないくつもの宮殿の点在する市街いっぱいに、そのチャイムが冴えた高いしらべを市民の心を宥めるように響かせていた。 市街の北部に聳える北岳、北漢山の岩肌の峯々を赤く染めた夕日が、その翳りを濃くして行く頃のひとときが、夕餉を終えてからの私の散策の時間だった。私は一人で、時には学友の江上と連れだって曹渓寺の丘に続く尾根道を、好きな寮歌を歌いながらゆっくり歩んでいった。その時間帯には朝鮮の青年たちも、近くの山陵でひとり或いは数名で朝鮮語の歌を声高らかに歌っていた。私も瞑想にふけるような調子で寮歌を歌い続けた。
私にとって昭和十二年の夏はこのような環境の中で休暇を過ごしていた。八月の旧盆には仏教各宗派の寺々の境内で浴衣姿の子供たちを集めて盆踊りが催されていた。八月十六日の夜、散歩から帰った私に、「卯一!昭子と和子が若草町のお寺に踊りに行ってるから、迎えに行ってちょうだい」と母が頼んだ。 寺の境内では小学生の妹たちが、近所の子供たちと一緒に輪をつくって踊っている最中だった。 「ここは朝鮮だ。朝鮮に内地人がどんどん増えて、日韓合併以前から韓国の首都だった京城では内地人が市民の五分の一を超えている。古くから京城に移住している内地人の中には、郊外に日本人墓地をつくり、そこに墓を建てた人々も増えている。いま盆踊りの輪の中に居る子供たちも朝鮮で生まれ朝鮮で育った者が多いだろう。そして多くの内地人がここに根づいて行くんだろう」このように考えていると、常々から私の胸の底に潜む、言葉には言い表せない不安めいた想いも拡がりはじめた。 私の母方の親族は親が合併以前の明治三十年代に京城に移住し、その子供たちは京城で生まれて四十歳代、三十歳代に達していた。家業は製粉製菓業だった。その中の一人には京城大学医学部の助教授も居た。父の姉は夫とともにやはり合邦以前に渡鮮し、北朝鮮の鎮南浦郊外で林檎農園を営んでいた。その長男は判事として平壌の裁判所に勤務していた。私の父は日本鉱業株式会社の技術社員として北朝鮮の鉱山に勤務し、家族を京城に住まわせている。私は大学予科の一年生、弟二人は京城中学に在学、妹二人は京城の日の出小学校に在学、末弟は三歳。このように自分の親族を改めて見まわすと、明治以来の大陸への日本国家の発展とともにそれに呼応するかのように多数の親族が京城をはじめ朝鮮に広く生活しているのである。いとこたちは、そしてその親や子供たちを合わせると私ども一家を含めて三十数名に達していた。 「内地人が朝鮮をはじめ大陸にどんどん増えていく。これが日本民族の生きて行くための必然的な成り行きなのだろうか。この現象を朝鮮民族はどのように感じているだろうか。確かに日本民族は朝鮮に根付き始めている。しかしこの根付き現象が、国力を背景に他民族の土地に侵入しているという性格を帯びているとしたら、それは日本民族の本当の根付きにはならないのではないか」 京城市街の南部に鎮もるようにどっしりと位置する、緑で蔽われた南山と称される山塊の西端の高台には、広壮な境内のある朝鮮神宮が建立されていた。天照大神と明治天皇を祀る官弊大社といぅ最高格の神社だった。この神宮が朝鮮全体の鎮守とされており、京城の鎮守としては京城神社が山麓に建てられていた。神社の秋の例大祭には内地人の多く居住する付近の町々から御輿が幾つも奉納され三日の間賑わった。昭和十二年は戦争が始まったので中止されたが、前年までは大規模な日本の時代風俗の仮装行列が街々をねり廻ったのである。内地を離れて京城に住みついた中小の商工業経営者たちが中心になって、郷里の町々に対抗して威勢を示す行事でもあった。私の母方の従兄弟たちの中でも長男の松本清衛叔父は、父の家業の製粉工場を継ぎながら町会や祭りの世話役として活動していた。 日韓合邦以前から京城で生まれ育った叔父は折に触れて私に語った。 「大正末期以降特に昭和五、六年を過ぎると、京城をはじめ朝鮮全土にわたって内地人が急増して釆た。三井、三菱、住友、日産、日窒等をはじめとする財閥系の営業部門や工場、鉱山の拡張、増設、開発。総督府をはじめとする全土にわたる諸官庁の横構拡充、学校教育機関の増設等々で、会社員、官吏、学校教員の増加は特にいちじるしい。 しかし内地人の多くはやがて転勤したり、定年退職後は内地に戻ろうとする人々だ。自分で商工業活動をしている人々も老後は内地で暮らそうと思っている人が多い。こんな根性じゃあ日本の大陸発展の地盤が固まって釆ない。朝鮮の地に根付く。そして朝鮮に骨を埋める。こんな気構えで頑張らなければ、出かせぎ根性、島国根性は改まらず、朝鮮民族からも心底で舐められてしまう」 このように言う際の叔父の言葉にはいつも熱と力が篭っていた。 「叔父さんは多くの内地人が朝鮮に住んで居ることができるのは、どんな力が背後にあると思っていらっしゃいますか。軍の力を背景に合併の条約を取り決め、武力を背景に十数年間にわたって行政を実施した威嚇政策の効果だとお思いですか」 私は普段から自分でもはっきりとは断言できない問題を問いかけた。 「そりゃあ、日本の国力だ」 叔父は更に言葉を続けて、 「日本の国力全体が朝鮮に浸透するとともに両民族の精神的融和もはかられているからだ」 叔父は言葉の調子を和らげて声を落として言った。 「日本の懐柔策によって、現在朝鮮人は表面は隠やかそうに見えるが、心の中ではそうではない。 叔父が私に、「もっといろんなことが体験を通じて分かって来るよ」と語った話の内容は、日ならずして私にも苦い体験として味わうこととなった。 十一月上旬の或る夜だった。日支事変がどんどん大陸の奥地へと拡がり始め、遂に山脈を越え、 私は解散後、個人的所用で学友たちと別れ、一人で南大門通りの歩道を黄金町の方向に向かって歩いていた。すると横町から朝鮮簿の学生のみが学んでいる私立の専門学校生が十数名余り、灯の消えた提灯を手にしながら三三伍伍歩いて来るのに出くわした。そして私を内地人学生と見ると、突然彼等は万歳! 万歳! と笑いながら叫んでとり囲み、その中の何人かが私の身体を肩や背で道端の石坂に押しつけて来た。多勢にたいし私ひとりである。彼等の嘲笑するような万歳の声や表情にたいし、私は着ている黒マントで身を包み、何も言わず、押される力にじっと耐えていた。付近を歩いていた人々が数人立ち止まったようだった。すると彼等は一段と声をはり上げて笑い、ばらばらと私から離れて立ち去って行った。押されて居たとき石塀で腕を擦りむいたのかひりひりしたが、上衣を脱いで汚れを払いながらしばらく私はぐっと唇を噛みしめていた。 嫌がらせを受けたのが悔しかったのではない。とり囲まれたのをさほど恐怖とは感じなかった。朝鮮民族の屈折した心理状態の捌口が私に向かって来たのをいきどおっても、それをどこにももっていきようがなかった。「彼等はこのようにして朝鮮を領有している日本国家への欝憤を晴らそうとし、また中国にたいして戦争を始めた日本の行動に批判をぶっつけているのか」とも思った。 それとともに、つい先刻まで一緒に提灯を振りながら肩を並べて歩いた同じクラスの朝鮮籍の学友の一人が私に告げた言葉を思い出した。 「どうして太原占領が万歳なのか、わからない」 その言葉を気にした私が思わず彼の方を振り向いたとき、鮮銀前広場のネオン塔のあかりが彼の濡れた頬を赤くやわらかく照らしていた。 |