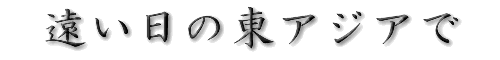
|
第二章 関釜連絡船
私は大阪からの帰路、関釜連賂船の夜行便で釜山を経て京城のわが家に戻る途中だった。昭和十四年(一九三九年)の三月末に、本籍の寺で身内だけで祖父の七回忌の法要が行われ、父が社用で出席できないために長男の私が学校の春休みを利用して参列した帰りなのである。 「乗船は何時噴から始まるんでしょうか」 私は山陽本線の車中で知り合った青年に話しかけた。 「普通、一時間位前からですよ。船の出発が十時だから九時頃からかな」 一緒に列に並んでいる青年が答えた。彼は三十歳位の国防色の服を着た満拓の社員だった。満州拓殖公社の本社に勤務しており、毎年社用で新京から内地に出張するらしかった。 「今夜の船は『興安丸』でしたね」と確かめると、彼はうなずいて、 「私たちは下関に早めに到着する列車で来ているからいいんですが、最終の急行で着く人々は、 「それでも興安丸のような大きな船が就航するようになってから、閑釜間の往来がぐっと楽になりましたよ。私が就職して初めて出張した五年前は、三千トンクラスの『昌慶丸』のような船でしたからね。それが今では七千トンクラスの船が昼便にも夜行便にも就航するようになって輸送にゆとりが出たように思えたんです。しかしそれも二年位で旅客増に追いつかなくなり、近く同クラスの連絡船が更に追加して建造される予定だそうですよ」 「連絡船の旅客がこんなに急激に増えるのはどんな事憎からなんでしょうか」 私はその原因を私なりに推測できたが、満州への移民業務を担当している彼の見解を聞きたかった。 「簡単に言えば、それは朝鮮および満州国の発展と日本内地への朝鮮からの労働者の需要でしょぅ。私の仕事に直接関係するのですが、日本から満州への農業開拓団の移住もその主な原因となっています。現在、主として農村から年間三万人位の規模で農民が満州に移住しています。それに日支事変が長期化した影響での軍需景気で、九州や北海道の炭鉱への朝鮮人労働者の移動もいちじるしい」 日本の大動脈である東海道、山陽本線の列車の終点、下関駅と、朝鮮から満州へと続く幹線鉄道の起点、釜山駅とを、玄海瀬や朝鮮海峡の海を越えて七時間余りで結ぶ関釜連格船は、日本とアジア大陸とを往来する旅客にとって、最短、最速の重要なルートだった。 朝鮮や満州に住む日本人が増え、日本内地に移住する朝鮮人が増えれば、それに伴って両民族の関釜間の往来も多くなるのは必然的な現象だった。 「農業開拓団としての移住者が多くなると入植地の確保もたいへんでしょうね」と私は未開の北満の広野を思い浮かべながら言った。 私の問いに彼は一瞬こわばった表情を示した。そして声を低めて言った。 「実は、入植地の大部分は満州の農民から買い上げた農地なんですよ。はじめから未開の原野を開拓することは、入植者たちが早期に自立するには到底無理な話しですよ」 彼がここまで語ったとき、私服の刑事らしい感じの背広姿の男性がつかつかと近寄って来た。思わずはっとして黙ると、目標は私たちではなく、列の二人前に並んでいた国民服姿の一人の男性だった。刑事は警察手帳をその男性に示してただちに彼を列から引離し何処かへ連行して行った。 九時少し前になって、旅客の列は少しずつ進み始めた。二列になって動く行列は駅のホームと桟橋の乗船口との間に最後尾が見えない程長く続いていた。二千名近くに達していたのであろうか。列が動き始めた頃から私服刑事による旅客のチェックもしばしば見受けられるようになった。手配中の思想犯や、家出人、各種犯罪容疑者の朝鮮、満州への逃亡を防ぐための措置らしかった。 私は白線二条の制帽、制服に黒マント、白い鼻緒の杉下駄をはいていた。いよいよ興安丸のデッキに上り三等船室の入口まで来たときだった。若い私服刑事が、私を見て、「責方は京城帝大予科の学生さんですね。一寸鞄を開けて下さい」と丁重に言った。時々学生に対して携行している書物のチェックがあることは友人から聞いていたので、私は別に思想的に嫌疑をかけられるものを持っていなかった。落ち着いて鞄を開けてじっとしていた。中には和辻哲朗の『人格と人類性』と岩波新書の『万葉秀歌上巻』が入っていた。刑事は学生一般に読まれている図書に詳しいのか単行本の『人格と人類性』を手にとって、「ああ 和辻さんの本ですか。『風土』という本も有名ですね」と微笑しながら言って、「はい、いいです。鞄をしめて下さい」と軟らかな口調でチェックを終えてくれた。 三等船室には寝台もあったのだが、二人ともその切符を買い損ねて居たので混雑した普通の船室に入り込まざるを得なかった。どんな船でも同じだが、三等船室は通路で幾つもに仕切られた絨毯を敷きつめた平座席である。引き続いて乗客が入って来るので、横臥する場所を確保しておかなければならず、私と満拓の社員は早めに並んで足を伸ばして座った。私どもの場所はまたたく間に満席になった。部屋の電灯は点したまま眠ることになるのであまり明るくはなかった。 「二等旅費を貰っているんですが、若いうちは三等で我慢しても大したことはなく、旅費はずいぶん浮きますよ」と彼は笑いながら言った。 私は仰向きながら、 「学割はありがたいですね。内地は二割引だけれど朝鮮内は四割引ですからね」 と言うと、彼は「それが満州国内では学生は五割引です。学生の満州への関心を深めるように旅行を奨励する趣旨もあるんでしょうね」と言って周囲を見廻した。お互いに譲り合って横になれば眠ることはできそうだった。 「私の会社に内地から就職した或る青年のことです。東京での学生生活中に知り合った女性と恋愛関係にあり文通を続けていたのですが、入社後二年たって彼が満州の北部の都市、桂木斯に勤務することとなり、いよいよ結婚を決める段階で、北満のような治安の良くない土地で働く男性に娘を嫁がすことは認めないと言って父親が強く反対したのです。その結果、娘は遂に親の金を無断で持ち出し、関釜連格船経由で朝鮮を経て満州の北の果てに近い町に住む彼のもとに飛び込んで来たのです。桟橋での私服刑事によるチェックには、このような家出人にたいする家族からの捜査願いによる場合もあるんですよ」 「民族を問わず連格船にまつわる男女の思いつめた物語りは胸に迫りますね」 船の出発を知らせるドラの音のあわただしい響きがつたわってきた。 私は彼の先程の話との関連で、開拓農民の入植する土地を確保するために、会社が満人の農民からどの程度の価格で土地を購入しているのかについて関心が湧いていた。しかしそんなことまで聞くのは彼の警戒心の様子から推測して、機密事項にも関わりがあると思って遠慮した。 私は話の方向を変えて、「前進座が出演して、和田伝の作品『大日向村』が映画化されるそうですね」と、思い出したようにぽつりと言った。 「あゝ、あの有名な長野県の大日向村の分村移住をテーマにした作品ですね。あの村からの開拓団の方々は、満州移住に積極的にとり組んだという表彰的な趣旨もあって、地理的条件の良い地区に入植されましたよ」 「河原崎長十郎や中村翫衛門が主演なら迫力のある映画ができるでしょう」 彼の説明は次第に熱を帯びて来た。 「朝鮮にも関係するんですが、やはり国策会社で鮮満拓殖という会社も満拓公社に統括されましてね。以前から満州東部の間島地方に農民として居住する朝鮮農民や北朝鮮から満州に移住希望の農民にたいする支援業務が行われています」 私は彼から拓殖事業の現況についてもっと聞きたかった。しかし船の小さな揺れや人いきれで疲れが増して来たし、他の人々の睡眠をさまたげることにもなるので、十一時にはお互いに眠ることにした。 三等船室の中は、内地人も朝鮮人もまた男女もいれ混じって、日本語や朝鮮語の話し声も聞こえて喧騒とまでは至らないが、複雑な雰節気がただよっていた。しかし乗客整理に馴れた国鉄(鉄道省)のボーイがてきばきと行動し世話するので船室の秩序はよく保たれていた。 このような船室の夜の時間を、眠るともなく横になっていると、私はいつしか自分自身が、そして日本民族が、また朝鮮民族が、ともに大きな運命の船に乗って地球の上を運ばれているような想いに駆られた。 そして朝鮮籍の学友が喫茶店で教えてくれた「涙の連絡船」の歌を復習するように頭の中で歌っていた。
「本当にあなただけ
私はこれらの列車のうち最も早く六時五十分に出発する京城行の「あかつき号」に乗車するので、駅の食堂でゆっくり食事をとる余裕が無かった。食堂での朝食を終えてから新京行の「のぞみ号」で出発する予定の満拓の社員とは桟橋駅で別れた。 私が「あかつき号」の窓際の席に座っていると、軽く会釈して明るい眼差しの二十七、八歳位の女性が前の席に座った。続いて私の横の席に私より少し若い十八、九の年頃の国民服を着た青年が座り、更に続いて斜め前の席に背広姿の三十過ぎの会社員風の男性が座った。みんな連賂船から列車に乗り換えた乗客たちである。私を含めて向かい合った四人は、列車が動き始めると一様に駅で購入した弁当を食べ始めた。四人とも同じ駅弁なのでくつろいだ雰囲気がただよい、誰からともなくよもやまの語らいが始まった。 女性は京城郊外の普通学校(朝鮮民族の児童の小学校)の教員であり、背広の男性は、京城電気会社の社員だった。国民服の若い青年は北朝鮮の都市、興南にある窒素肥料工場の技術員として追加応募に採用されて赴任途中の、山口県の工業学校の卒業生だった。その青年は、興南の日窒系の工場は国際的にも屈指の優れた設備を有する大工場であることを誇り、希望に満ちた口調で胸を躍らせていた。 「会社の俸給もとても良いんです。内地では工業学校卒は初任給が五十円位ですが、ここでは八十円の月給なんです」と言って、会社の施設のガイド写真帳を広げた。それには大規模な窒素肥料工場や化学工場を始めとして、その工場の必要とする電力を得るための二つの大きなダム。またダムによって鴨緑江を上流の蓋馬高原地帯で、堰き止めて造った長津湖、赴戦湖の二つの湖。それらの湖水をトンネルで日本海側斜面に誘導し、一、〇〇〇メートル余の落差を数段に区切って作られた幾つもの発電所、海岸の工場地帯と高原の湖畔を結ぶ鉄道、路線ケーブルカー等々が紹介されていた。 「私の郷里は四国の徳島です。五年ぶりに帰郷して来ました」と、私の前に座っている女教員が語り始めた。 「郷里の女子師範を卒業して京城女子師範の演習科に入学し、卒業して朝鮮の児童たちの学ぶ普通学校の教員になりました。今は水原の近くの学校で教えています。朝鮮の生徒たちに接していると、みんなが熱心に真面目に学習するし私によく親しんでくれるので、心からやり甲斐があります。 生徒に愛情が湧けば湧く程民族の異なることを忘れるようになり、私の朝鮮語も生徒たちの日本語も共に上達し、毎日充実した想いで頑張っています。朝鮮の風習や生活様式も知りたくて、結婚前は地元のある両班の屋敷の一間を借りて住んで居たんですよ」と彼女は快活な口調で語り続けた。そして、「今度の内地旅行で面白い体験をしましたわ」と言って少し間を置き、「郷里から戻る途中、昨日下関行の急行列車に岡山から乗車したときのことです。前の席に居た五十過ぎ位の背広姿の男性が私に話しかけて来ました。 「あんたはん、何処へ行きはりまっか」 住んでいるという言いかたで答えたのだから、私の言葉のニュアンスでもう気がつく筈だと思いましたが、そんな気配はありませんでした。 「そうだっか。それにしてはえろう日本の言葉が達者でんな」 私はじれったくなって、このまま朝鮮の人になり切って話しを続けようと思いました。 「そうですか。私は学校で熱心に日本語の勉強しました。内地の人と変らない位上手に聞こえますか」 ここまで私が言うと、相手の男性の表情はややけげんそうな感じになって言葉の調子を改めてきました。 「関西では朝鮮のお人は、工事場の人夫はんや古物買いの貧しそうなお人が多いけど、朝鮮にはやっぱり地主はんやお金持ちもぎょうさん居はるんでしゃろなあ」 と声を落として言いました。私は少しでも朝鮮民族の誇りを朝鮮への認識不足な内地の人々に知らせたいと思いました。そして、 彼女がこんな風に話していると、それを横の席で聞くともなしに聞いていたらしい三十過ぎの会社員の男性は、苦笑を浮かべて眼をつむっていた。 女教員の話が一段落すると彼はおもむろに口を開いた。 「内地の一般の人々の朝鮮にたいする認識の足らなさ、というよりも無関心さですかね」 彼は私の意見に領きながら、 「田舎の農家の年配の人々の多くは、朝鮮が日本の領土になっていると言っても、やっぱり遠い外国のように思えるんでしょうね」 と言って数年前の思い出を語りだした。 「私の本籍は秋田県ですが、奥羽線の列車で向かい合わせに座った初老のお百姓さんらしい服装の男性が、私が朝鮮の京城に住んでいると言うと、こんなことを問いかけて来たのです。 「朝鮮という土地は、今でも虎こが出るだべか」 あまりにも時代錯誤の問いだったので、 「どんなとこさ居るだべか」と真顔で問い返して来るので、私は笑いながら「動物園にですよ」と答え、言葉を続けて、 とかいつまんで説明しました。すると彼ははっとしたような表情で語り始めました。 「そんだら安心だし。実は俺らの末の息子が去年兵隊にとられて、今朝鮮の会寧というところの連隊に居ます。手紙が来てもあまり詳しく言って来ねから、どんな処かわかんねで心配ばかりしてたども。上の息子は召集で満州の部隊に居るべ。兵舎のあるところは町から離れた淋しい場所で、冬は零下三十度を越す寒さだと手紙さ書いて寄こすました」 それを聞いて私は故に対してぐっと、同情と敬意がこみあげて来ました。 「会寧は朝鮮の北のはずれですが、大きな町です。満州の部隊は場所によっては遠くて行くのは大変だけど、会寧までは新潟から船と汽車で、ここから二日ぐらいで面会にも行けますよ」 話しているうちに列車は大邱を過ぎ、洛東江を渡り秋風嶺を越えて昼頓には大田駅に着いた。 女教員はここで下車した。未だ学校が春休みなので、教員をしている夫と共に「扶餘」を見物するため大田駅で待合わせの約束をしていると楽しそうに語っていた。 青年は汽車弁が好きだと言って駅売りの弁当を貰って来た。 私は京城電気の社員と連れ立って食堂車に行った。食堂車は昼食時なので混んでいたが食事を終えて立ち上がった二人連れが居たので選良く席を確保できた。 席につくと、斜め前の窓際の席で食後のコーヒーをすすっている初老の紳士が居た。その顔は写真で見覚えがあった。大学の安倍能成教授だった。私は未だ予科生なので、校舎の場所も異なりこれまでに一度も接することは無かったが、著名な哲学者であり特徴ある風貌は記憶に鮮明だった。 挨拶して自己紹介を述べると、教授は静かに重々しく頷いて、 大学の法文学部は専攻が「哲学」「文学」「史学」「法学」の四学科に分かれていた。予科からは自分の志望で専攻を選ぶことができた。私は予科に入学した当初は史学を志していた。中学時代の恩師や叔父が以前から私に勧めてくれていた影響もあったが、私自身も歴史や地理が最も得意な科目だった。しかし予科に学び学友と接するうちに民族問題に関心が強くなり、専攻部門をどうするかに迷いが出始めていたのである。 「未だ決めかねています」と答えると、教授は、「そうか、慎重に考えるんだな」と微笑を浮かべながら窓の方に瀕を向けられた。そして、 毎年三月から四月の始めにかけて、アジア大陸の奥地から黄砂を含んだ風が朝鮮半島の中部以北の空を蔽うように吹く日があった。蒙古やゴビの砂漠地帯からはるばる吹いて来るのであろうか。北支や満州では「黄塵万丈」と表現され、黄砂の量が非常に多く目も開けておられないぐらいだそうである。朝鮮の上空もこの風が吹いている日は、空が薄黄色に染まっていた。 「この風を吸うと呼吸器に悪い。君はあまり丈夫そうに見えないから、気をつけるんだな」 初対面の私に思いやりある言葉を残されて、安倍教授は一等車の方へ戻って行かれた。 「さすがに帝大教授の風格がありますね」と京城電気の社員が言った。そして、「高商の学生の頃安倍先生の随筆を新聞で読んだんですが、それによると、教授は東京と京城の両方に住居を持ち軽井沢に別荘を持って生活しておられるようですね」 京城生活が東京生活の延長のような意識で生活している人々。それは総督府の高官たちの中にも帝国大学の教授の中にも、また東京に本社のある銀行、会社等の大企業の幹部はじめ社員たちにも多かった。京城が大陸における日本の首都としての機能が満たされれば満たされるだけ、それは東京の姉妹都市としての性格を持つ都市として京城における東京生活の世界が拡大された。他方平行して増加する京城や朝鮮各地に根付いた意識の内地人の世界もまた拡大されて行った。 しかし拡大し発展する大企業の工場や事業所や内地人の経営する中小の商工業の労働者、特に作業現場の労働者は殆ど全部が朝鮮人だった。 「私の会社の事業の一つである京城の市内電車やパスの運転手と車掌は全部朝鮮人ですよ」 内地人の間でよく話題になるこの錯覚話を、私が彼との語らいの中で改めて語ったとき、ふと私の頑の中にひらめいた思いがあった。 京城でも東京でも、市内電車の運転手やバスの車掌はみんな同じ職種の労働者なんだ。民族は異なってもみんな同じ職種の労働者なんだ。そこに民族を超えた連帯感は生まれ出て来ないんだろうか。日本の大企業系の工場や鉱山が年とともに朝鮮の地に増加していく。そこに働く労働者はみんな朝鮮人の労働者だ。しかも同じ職種の内地人の労働者は日本内地にますます増加している。日本民族と朝鮮民族とは労働者としてどのような関係になって行くのか。 私がこんなことを思いめぐらせていたので、僅かの間だったがカレーライスのスプーンを口に運ぶのを止めていた。 「どうかしましたか」と彼は私に不審そうにたずねた。 「いや、一寸思いついたことがあって」と私は言葉を濁した。 窓の外は黄砂の風で景色が黄色に曇っていた。列車は大田から京城までの間を二時間余りノンストップで走る。 成歓という駅の表示を、列車は四十数年前の日清戦争のまぼろしを見るように、またたく間に走り過ぎた。 |