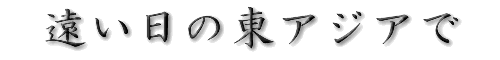
|
第三章 汝が祖国わが街
満州国では、農業開拓団の日本からの移住が年を追って増加し、鉱工業の開発は益々軌道に乗って発展していた。北朝鮮地区と南満州地区の工業化は日本の大陸発展の産業基地を目標に計画され進展していた。 必然的に京城は大陸における日本の首都的役割をも帯びて人口の増加も著しく、内地と朝鮮、満州間の人々の往来も月を追って増加の一途を辿っていた。 十月も下旬の夕方六時頃だった。放課後の弓道の練習を終えて帰宅の途中、私は電車で朝鮮銀行前広場まで行き、本町通りの書店金城堂に立ち寄ることにしていた。 停留所からロータリー式に整備された広場を通って三越京城店前まで来たとき、夕方の人混みの中から、 「お!、金君」 私は思わず彼の手を固く握って、「しばらく振りだったなあ、一寸体調をくずして医者に注意されたので、半年程養生のため通学以外は家に引っ込んでいたんだ」 金青年はうなずいて、そして言葉を改めて、「中村さん、実は近い内に『志願兵訓練所』に入ります」と力強い語調で語った。 「え、志願兵に」 「はい。いろいろ考えましたが、決心して志願しました。採用されたので十二月に訓練所に入ります」 彼はたんたんとした口調で答えた。 「とにかく何処かでゆっくり話を聞こう。今夜は都合がいいの」 「仕事は終ったんですが、店の宿舎に住み込みなので、一寸帰って連絡して来ます。三十分程待って下さい」 「いいよ。この先の金城堂という本屋にいるから」 昭和十四年(一九三九年)度は朝鮮民族にたいする志願兵制度が施行されて未だ二年目だった。日本政府は朝鮮民族が兵役について銃をとることに未だ信頼を置きかねていたし、総督府も時期尚早と考えていたようだった。しかし軍部の国政にたいする勢力浸透の強まった結果、戦争の拡大と兵員増加の必要から遂に総督南次郎大将をして志撤兵制度の早期実環を決行さすに至ったのである。これに志願することは、本人にとっては勿論深刻な決意に基づくことながら、それは朝鮮民族としては民族の運命にかかわる関心事だった。 私が初めて金成佑青年と知り合いになったのは昨年の九月中旬の日曜日である。長谷川町にある総督府立図書館の地下食堂だった。大学予科の学生の頃は私は月に少なくとも一度は、日曜日の朝から午後にかけてこの図書館を利用して主として文学書や小説を読みあさった。アンドレ・ジイドの『狭き門』やノヴーリスの『青い花』に陶然となり、読後の酔いの醒めないまま明治町の繁華街を通り抜けフランス教会の坂道を上り下りして大和町の自宅まで二キロメートル半の道を歩いて帰ったこともあった。 昼食は地下の食堂で四十銭の肉どんぶりを食べた。たまたま彼とは同じ食卓で出会うことが重なり、どちらからともなく話し合うようになっていた。今年の春頃までに六、七回は会う機会があり、帰りに街の喫茶店で語り合うこともあった。 彼は二十歳で私と同じ年頃だった。郷里全羅北道の群山の普通学校を終えて上京し南大門通りにある内地人の経営する工作機械問屋で働いていた。日本語はよく話せたし、誠実な人柄と数字に強い才能が認められて、店主からも同僚の内地人店員からも信頼されていた。語り合う機会が重なるにつれて、彼は次第に私にたいして心の底を打ち明けてくれるようになった。彼は簿記を勉強して将来会計業務で身を立て商店の経営者になりたいとの抱負を持っていた。彼の父は群山という港湾都市でトラックの運転手をしており、彼は次男だった。 彼の勤務する機械問屋は、使用人が八名余りおり、金青年ともう一人の十七歳の朝鮮籍の男のほかは、六名の店員全部が主人と同じ熊本県出身の男たちだった。主人は五十代半ばの温厚で経営の才豊かな人物だった。熊本の同種の問屋で働いていたが、大正年間の初め、志を立てて京城で同郷の先輩の援助を得て店を開き、次第に仕事を発展させて現在に至っていた。商品はポンプや工作機械の部品を取扱っていた。 日支事変が始まる二年前、店員の一名は徴兵適令で熊本の連隊に入営し、中支戦線を経て今年の六月に上等兵で復員し店の勤務に戻っていた。二十八歳の店員は四月に現地召集で京城の龍山にある歩兵第七十九連隊に入隊し、現在は山西省の戦線に出征していた。金青年と同じ年齢の店員は一年後には現役で入営する可能性が強かった。三十五歳の番頭格の店員は戦争が長引く形勢の今日、召集がかかる可能性があった。将来主人の後継者となる予定の息子は、京城の高等工業学校の機械科を卒業後入営し、陸軍幹部候補生から予備役工兵少尉に任官し引続き召集を受けて北朝鮮の羅南の第十九師団の連隊に配属されていた。 このように戦争の長期化とともに、内地人の店員が兵役との関係で落ち着かない立場に置かれるようになると、店では朝鮮籍の店員だけが安定して仕事を続けられる当てになる存在となった。除隊して来た二十三歳の森田店員は、先輩店員の中では金成佑青年にとって最も親しみをもって接することの出来る店員だった。おおらかな性格の兄貴にたいするような気持ちで彼は森田店員を敬愛していたし、森田もまた彼をよく指導し面倒を見てくれた。 金青年は図書館からの帰途、コーヒーをすすりながら私に語った。 「私は先輩の内地人の店員たちが、入営したり召集されたりして軍隊に入り戦地に赴くことを、国民の義務として割り切って仕事をしているのを見ています。割り切っているような言葉や行ないを示していても、それぞれのいろんな心の中の動きが胸に伝わって来るのです。そしてその心情にたいして同情や尊敬の想いも湧いて来ます。しかしそれとともに、私の胸の中にはこんな気持ちも湧いて来るのです。内地人たちは日本という愛する祖国があるんだ。自分たち朝鮮民族の祖国は三十年余り以前に日本に併合されてしまっている。そして日本はわれわれに対して『貴方たち朝鮮民族の祖国は今や日本なんだ。朝鮮民族も日本国民となっているんだから、日本を自分の祖国として愛するようにならなければいけない』と指導する。しかし私はどうしても日本を祖国とは思えない。自分の祖国は韓国だという感情が胸の底からこみ上げて来ます」 私たちは語らいながら、ある日は長谷川町から太平通りへそして南大門通りへと舗道を歩き廻ることもあった。 「私の働いている店の主人も店員たちも、男らしいさっぱりした人たちが多く、私は不愉快な想いを殆ど味わうことなく過ごしています。それだけに外で時々体験する内地人の民族差別的態度や言葉には一層敏感になります。主人は仏教の信仰が厚く民族間の問題にも常々から細かい心くばりをなされるお方です。去年の夏こんなことがありました。中元の贈答用に店名の入った手拭を作りそれを店員たちにも配ってくれた時です。もう一人の朝鮮籍の店員の李君に配られた手拭だけが油で大きくしみが付いていました。彼は申し出て取替えてもらいましたが、それを横で見ていた主人が、『済まなかったね』と彼に言葉をかけて詫びました。そして丁度そこに居合わせた内地人の店員たちを次のように諭したのです。 『たまたましみの付いた手拭が李君に手渡されたんだけれど、民族間の感情はこのようなことにも気をつけなければいけないよ。しみの付いた一本の手拭が他の多くの内地人の店員に渡らず李君のみに手渡されたということは、手渡す人に他意は無くても受け取った本人はこれを被差別感情として感じることにもなるんですよ。内鮮融和をはかり、更に最近は内鮮一体という目標が叫ばれているが、特に内地人は今言ったような心くばりをするよう努める必要があるんですよ』 私も主人の諭しを一緒に聞いていました。そして主人の細かい配慮を感謝の心で受けとめていました。しかし同時に感謝とばかりは受けとめられない感情も湧き起こって来ました。 「つまり自分たちの民族は、優越性を強く意識する日本民族に慰めてもらっていることになるんじゃぁないか。日本国民にされ国を失った朝鮮民族を憐れんでくれているのを感謝していることになるんじゃあないか。と思うと情けなくなってしまうんです」 私は彼から朝鮮民族として思い悩んでいる心情を聞きながら、その都度それにたいするまとまった答えができない自分自身を常にじれったく思っていた。 四月中旬になって、私は学校の身体検査で血沈やレントゲン検査の結果、肺浸潤の初期と診断された。微熱の出る日もあるような健康状態になったので、学校には通うものの病気養生のため五カ月余りは図書館通いも中止し、彼との出会いも途絶えていたのである。そして九月の中頃になって体調も良くなったので、図書館に行って彼に会う心積りにもなり始めたところだった。 金城堂書店で五十分余り、本を立ち読みしたり主人と話したりして時間を過ごした。金成佑に夕食をおごるために予定していた本を買うのを取り止めた。 急ぎ足でやって来た彼は、 七時頃になって、精乳舎のレストランで向かい合って夕定食のランチをゆっくり口にしながら、私は金成佑から彼の志願兵となった理由を聞いていた。 「私は日本人に同情されていることに甘んじて居ることが我慢できなくなりました。考えの飛躍かも知れませんが、内地人と同様に日本の軍隊に入る。そして内地人とともに軍隊の訓練を受け戦場にも行く。そして自分の生命をかけて先ず国民として内地人と同じ立場に立つ。そしてたくましい兵士として精神的にも肉体的にも立派に朝鮮民族の将来を背負って立つことのできる人間となる。 私は形としては日本帝国の兵士となるのですが、目的は先ず第一段階として、朝鮮民族が日本民族と対等の立場での国民として力を発揮できるようにしたいのです。私は朝鮮民族のためにその第一歩を志願兵として踏み出したいのです」 ともすれば声が高くなる彼の言葉を私は自分の唇に指をあてて制した。彼の言葉の内容は憲兵に知られると不穏当な思想として受け取られる傾向を含んでいた。しかしそれでもなお彼の言葉は自分の本当の胸の中を押さえての言葉だろうと思った。その胸の中とは朝鮮民族の意識の中に脈々として潜んでいる民族の独立回復への熱望だった。将来の独立の日のために、志願兵制度を通じて魂は朝鮮独立軍兵士として、形は日本帝国の兵士となることだった。私は金成佑の真剣なまなざしが、それを何よりも雄弁に訴えていると思った。 「店の主人や店員さんたちはこれを‥‥」と私が問いかけると、 「今話した私の本当の気持ちは、店の主人にも、店員たちにも誰にも話していません。森田さんは『軍隊とは国立の人間修業道場だと思えばいい。この修業を乗り越えれば心身ともにたのもしい人間になれる』と言って励ましてくれています」 金成佑は思い込んだらその意志を曲げない内向性の強い性格だった。軍隊入りを志願する心情には未だかなり弾力性が感じられ、熱意を転換させることも可能だったかも知れない。しかし事ここに至っては、私にはそのための説得をする余裕も、まとまった考えをももっていなかった。 「わかった。元気で頑張ってくれ」 私は語気を強めて彼の手を固く握った。 彼は志願の理由の説明で紅潮した頬を落ち着かせて、 彼がてれくさそうに、うつ向きかげんに言ったので、私は、 「いや、結婚なんて。朝鮮も家族制度やしきたりが厳格でしてね。それに相手が酒場の女の場合、私の家では望んだって許されることはありません」 そのスリチピは南大門通りを鐘路通りの近くまで行って細い道を東に少し入った裏町の小さな酒場だった。テーブルが二つありチャプ台を含めても客は十二、三人入る程度の広さだった。三十代位のマダムらしい女と、十七、八から二十過ぎ位の女性が三人の、こぢんまりした雰囲気だった。他の客は四人だった。私たちは空いているテーブルに向かい合って座った。 内気そうな娘が金青年の横に、明るい感じの少し年上の娘が私の横に並んだ。二人とも金君とは既に顔見知りになっており、金君の横に座った娘は、先程彼が私に語った娘だった。黄色のチョゴリと紅色のチマがよく似合う、小柄な細おもての、瞳のすがすがしいチョンニョ(女の子)だった。私の横の娘は日本語が少しは話せたが、彼の横の娘は殆ど話せないようだった。 キムチを肴にマッカリ(朝鮮酒)を飲んだ。彼は酒が強そうだった。私はアルコールに弱いので、もっぱらキムチを食べていた。辛さを湯で薄めながら食べたが美味しかった。自然に彼は彼女と、私は私の横の娘と話し込むようになった。私の横の娘は江原道の日本海に沿った漁港、長箭町の出身だった。 「長箭はいわしが沢山獲れます。いわしはただみたいに安いです。そしてとても美味しいです」 とおぼつかない日本語で語りながら、明るい表情に蔭りを見せた。 「そうだ、そうだ、歌いましょう」と言いながら私の横の娘に「イルポン(日本)の歌。タンシンの一番好きな歌、歌おう」と呼びかけた。彼女は、 「花も嵐も踏み越えて 私は歌いながら金成佑の横の娘に目をやったが、彼女は歌っていなかった。 「この娘は未だイルポンマルできないし、イルポンの歌、歌えないよ」 「そんなら今度はアリランを歌おう。僕も知ってるから」と私は言った。 「アリラン アリラン アラリヨ 私は一番目の歌詞しか知らなかったので、 私の横の娘は私に、「あの娘は、こう言っています。志願兵にならないで、あなた戦争に行って死んでしまう」と通訳してくれた。 金成佑は彼女の肩を抱きながら視線を私からそらしていた。 やがて彼は支払いのため立ち上がってマダムのところに行き、何か立ち話をしていた。私は娘たちにチップとして五十銭ずつ手渡した。そして泣いていた娘に、 娘は私の言葉の意味をつかもうとする表情で私を見つめていたが、 彼女の両肩に垂れさがった巻き髪が、薄明るい電燈の下なのに、つやつやとして美しかった。 それから十日余りたった土曜日の午後、私は久し振りで星雲短歌会の例会に出席した。会場は帝大門通りの丁字屋デパートに近い喫茶店の二階の和室だった。会員は京城支部長が先輩の大学の法学科一年の沼沢五郎さんで、学友の吉田をはじめ予科下級生の文科生、理科生各一名、銀行員、会社員や府庁(市役所)の職員が男女併せて四名、私を含めて出席者が九名だった。金子薫園主宰の歌会として全国的に組織されていた。東城には当時アララギ歌会をはじめとして日本で著名な歌会の支部が十指に余る程開かれており、東城日報は北原白秋を選者として一般から短歌を募集していた。 「柴積みし牛車の列はながながと鈴揺らしつつ街道を行く」という慶州郊外の風情を詠じた私の歌も紙上に選ばれたこともあった。大学予科に入学した早々に私は学校の短歌会に出席し、国文の須藤松雄教授や先輩の石原美樹雄さんに指導を受けて来たが、須藤教授からアララギに入会して基本から指導を受けるよう薦められていた。しかし躊躇しているうちに学友の吉田伸一君の強い誘いで星雲歌会の方に入会していたのである。 歌会の批評会にその日出詠した短歌は、 「短歌に朝鮮語を用いることによって効果的にその場の情景描写がなされている」と言われて、沼沢さんは私の大胆な表現を評価してくれた。朝鮮語が日常的に内地人社会にも通用するケースは次第に増えて来ているものの、未だ短歌に用いられている例は殆ど見当らなかったのである。 これにたいして、銀行員の会員から異論が出た。 これにたいして会社員の女性が云った。 「此の歌は単なる状況描写と言うよりも、臼本語の普及行政にたいする朝鮮民族の抵抗心理を詠んだものとしての意味に受けとることができるのではないか。そうとすれば少女は朝鮮民族でなければならず、少女は日本語を解せないし話せないから、歌の用語も内地人に通用する朝鮮語で表現するのが一層効果的なのだと思う」 司会者としての吉田が、「この辺で作者からの説明を」と云った。 「作者がその少女の言葉の語調やしぐさを通してういういしい美しさに感動しているのだから、その感動が伝わってくるなら歌としても成功しているんじゃあないかな」と府庁の職員の会員が云った。 「最初にイルポンマルモラヨが出て来るので、この言葉のイメージが強く迫って来る。決してさらっとした軽い感じの歌境ではないと思う」と会社員の会員が語気を強めて云った。 司会者、吉田は、 こうやって批評し合っているうちに夕暮れが迫り、歌会を終えて明治町通りを連れ立って歩いて行くと、松竹映画の封切館明治座からどっと観客が溢れ出て来た。その人々の中に一年先輩で大学かの文学科で日本文学を専攻している葛城真太郎さんが居た。彼は予科から引続いて大学の短歌会の委員をしていた。私は現在委員をしている予科の短歌会との連絡事項について彼との相談があるので、他の会員たちと別れて繁華街からフランス教会の下の坂道を上って行った。歩いているうちに用件が済み何処かで休憩しようということになった。私たちは永楽町と本町三丁目の交叉するあたりに近い「ハイデルベルヒ」という小さな喫茶店に入った。 そこでは二十代も半ば位に思われる女性客二人が向かい合って話していたが、私たちが入って行くとその中の一人は葛城さんの知人だった。相互に友人を紹介してくれた。彼女の連れの女性は朝鮮の女性で日本女子大の出身、彼女自身は東京女高師の出身だった。それぞれに京城の公立高女、公立女高普の英語の教師をしていた。 土曜日の夕方という気楽さもあって、初対面の間柄ながら四人は気の置けない雑談を交わしていたが、葛城さんが思い出したように、「中村君、今日君が歌会に出した短歌を披露してお二人の感想を聞いたらどう」と言った。私は初対面の年上の女教員たちに拙ない作品の感想を聞くのは気後れがしたが、葛城さんの口添えに力を得て原稿用紙に大きな文字で先程の短歌を書いた。 葛城さんは私から歌の内容の説明を聞いて、「カラフルなチマとチョゴリを着た金髪の朝鮮少女の素朴な可憐さがよく詠われていると思う。しかしイルポンマルモラヨと答えてうつ向いたという表現にこだわって考えると、この歌は理屈っぽい歌となってくる」と言いながら知人の女性の方に感想を求めた。その女性は、 ここまで彼女が感想を述べたとき、その言葉を引継いだ形で朝鮮籍の女教師が云った。 私は彼女の推測が私の歌の情景をよく言い当てていると感じた。酒場の朝鮮少女が、日本の志願兵訓練所に自分の意志で志願して入所する恋人にたいしていだくやり場のない悲しい恋情、そして涙。その少女にたいして「泣かないで、金さんに心配かけないで」とお説教じみた言葉をかけて慰めてあげた積りになっていた自分のあの場での表情はどんな顔付きだったんだろうか。少女が日本の少女ならばごく自然な慰めとして受け入れられる言葉も、民族が異なり個人が置かれた立場が異なる場合には当然のことながら同じようには受け入れられないことを、私は今更のように反省しわきまえなければならないと思った。 二人のインテリ女性からよくうがった感想をもらった私は、学生の身分のあつかましさからもう一首の歌についても、と欲が出て来た。 「時間がたったけれど、済みませんがもう一首の歌についてもご感想をお願いできませんでしょうか」と言いながら皆の衆を見廻した。みんながうなずいてくれた。私はまた原稿用紙にその一首を大きく書いた。 「汝がまちといらえくれるや我がまちと秋の日冴ゆる京城を呼ぶ」 この歌は未だ誰にも見せたことの無い歌であり、その心境はまだ誰にも語ったことの無い心境だった。 私は京城という都市に深い愛着を感じていた。街の北側に峨々とした岩肌の北漢山、三角山、仁王山等の峯々を背負い、南側に松の緑豊かな南山を抱き、洋々と水量ゆたかな漢江が西南部の平地を潤していた。近代的なビルが幾条もの市街に並び立ち、幾箇所もの、広い庭園に囲まれた宮殿や高く聳える都門が落ち着いた甍の屋根を拡げ、小高い幾つもの丘の上に大小のキリスト教会の尖塔が聳え立っていた。そしてそれらの風物が市街全体と調和して朝の光に輝き夕暮れの色に染まっていた。 このまちを都城として長い歴史と伝統を維持する朝鮮民族。明治維新以降、近代化に邁進し島国から大陸国家へと抱負を延ばそうとする日本民族。その両民族の綾なす複雑な民族感情。朝鮮民族の苦悩と日本民族の緊張とを癒すように、夕暮れの街に鳴りわたるフランス教会のチャイム。 「この歌から京城という都市にたいする私の想いをどのように汲みとってもらえるでしょうか」 「このように自分の住むまちに対する愛着を訴える歌の場合、愛着を観念的にではなく、具象的に訴える素材が効果的に詠われているかどうかが重要だと思う」 「そうすると『秋の日冴ゆる京城』という語句が愛着を表わす素材として問題になりますわね」と知人の女性が云った。彼女は更に続けて、 「確かに一年中で秋の京城が最も美しい」と葛城さんはうなずきながら言った。そして、 するとじっと考え込んでいた朝鮮の女性が口を開いた。 私は彼女のこの感想を聞いて、私の胸の底の想いを適切に推察してくれたと感じた。 彼女の名は李明姫といった。喫茶店を出てから、私は本町二丁目の古本屋日韓書房に欲しい本を見つけてありそれを購入する予定だったので、鮮銀前から電車で帰宅するという李明姫と連れだって本町通りを二丁目の方に向かって歩いて行った。 李明姫はすらりとした姿勢で歩み、胸元からの紺色のチマがよく似合っていた。 「わがまちと呼びかけた貴方にたいして、京城のまちが汝がまちとこたえてくれるだろうかという中村さんの京城にたいする想いはよく解るような気がしますわ」と並んで歩きながら彼女は語り続けた。 「このような気持ちは、京城で子供の頃から育った内地人にはあまりしっくりとは受け入れられないかも知れません。この気持ちは内地から京城に移り住んで幾年かたち、京城に愛着を感じた内地人の方の気持ちだと思います。 私は東京で女子大生生活を四年過ごしました。そして寮生活、父の知人の日本人宅での下宿生活を通じて、東京の牛込から小石川のあたりがとても気に入り、町の人々や学友もみんな親切だったので、私にとってはこのあたりをわがまちと心の中で呼びながら暮らすことができました。しかし、ほかの地域、ほかの場合に自分が朝鮮人だと改めて思い直さなければならないこともしばしばあって、そのためにすんなりと『わがまち』と呼ぶ自信が湧かなくなってしまうことも体験しました」 「そう言えば先程の葛城さんは、私のこの歌の気持ちにあまり感動してくれませんでしたね」 話し合って歩いているうちに、二人は本町から外れて旭町の住宅街に入っていた。 「今日は別に予定がありませんから、いいんですのよ」 彼女の日本語は訛りが無く声がさわやかだった。 「ええ、そうしましょう。そしてご一緒に京城の夜景の素晴らしさを味わいましょう」 私どもはゆっくり坂道を上り、南山の山腹のゆるやかな勾配の参道を語らいながら歩んで行った。 「葛城さんのようにこの地で生まれこの地で育った内地人の場合は、京城が故郷であり、故郷である京城は自分のまちだと当然に思って居らっしゃるでしょう。日本が朝鮮を合併して領土としているといういきさつはあっても、ここで生まれここで育った人は、朝鮮人はもとより内地人にとっても、ここがふるさとであり『わがまち』なのですから。そしてここがふるさとである内地人にとっては、『わがまち』と呼べば『汝がまち』と京城のまちはこたえてくれると思いこむことが自然の感情だと思います」 李明姫は私の方を向いてはほえみながら、「そんなことはありません。中村さんのような心境は、内地から移り住んでこのまちを愛する内地人たちが、自分で自分の胸の底を深く洞察してくれれば必ず到達する筈の心境だと思いますわ」 南山の中腹にある朝鮮神宮の境内の展望所には、私たちの他にも六、七人の参詣と見物を兼ねた雰囲気をただよわす人々が休憩していた。中年の国民服の内地人の男性二人と、朝鮮服を看た老人夫婦とその家族らしい人々だった。 眼下に無数の電燈のあかりが拡がって美しくまたたいていた。ビルの窓々にも、そして果てしなく続く市民の家々にも。人口百万に近い京城の街の灯のきらめきは、晴れわたった夜空の星のきらめきと相照和して深く大きく息づいていた。 「僕の まち だ」 「私の まち よ」 |