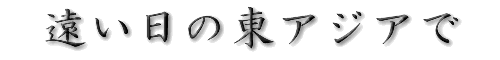
|
第四章 民族のしがらみ
京城から北に向かって、日本海岸の元山、咸興、清津、会寧を結び更に満州国の鉄道に連結して牡丹江に至る国有鉄道を「京元本線」「咸鏡本線」と称した。この鉄道で三時間余り北に行くと、朝鮮半島の中央部、平康高原の入り口に鉄原という町があり、ここで名勝「金剛山」に向かう電鉄に乗り換え、一時間余りのところに昌道という町があった。 鉱業所長としての朝鮮における父の最初の勤務地は、ここから四キロメートル余りのなだらかな丘陵の中腹にある、金華鉱山という硫化鉄鉱を採掘する鉱山だった。従業員は二百名余りで、そのうち内地人は技能者、事務職員を合わせて約三十名だった。ここで選鉱された鉱石はトロッコで呂道駅に運ばれ、列車輸送で北朝鮮の興南にある日窒系の大規模な化学肥料工場に運ばれた。労務者は全部朝鮮人であり、技能職員、事務職員の中にも一部朝鮮人が含まれていた。社宅は労務者用、職員用があり、内地人職員は約半数が世帯持用の社宅に入居し他は合同宿舎に入っていた。内地人のための小学校が遠いので学齢期になると家族を都会地に置き、夫は単身赴任で合同宿舎を利用する人が多かった。この鉱山は京城から半日の行程なので、私たち兄弟はしばしばこの鉱山の父の宿舎を訪れ、時には「金剛山」のすばらしい景色を味わうための小旅行の足場とした。 昭和十四年(一九三九年)の九月、父はこの鉱山から二百キロメートル余り北に位置する箕州鉱山の鉱業所長に転勤した。この鉱山は朝鮮半島の中央分水嶺となっている狼林山脈の谷あいに在った。臨津江の源流に沿って採鉱場、選鉱場そして従業員の社宅が並んでいた。このような地形の渓谷沿いは、通常なら人間の住めるような場所ではなかった。しかしタングステン鉱という貴重な鉱物が採掘されるので、土木技術の発達とともに、従業員は三百五十名余り二千名に近い人口の鉱山聚落が発達していたのである。そして鉱山と尾根を隔てた隣接の渓谷にも、箕州鉱山と同規模の百年鉱山が開発されており、大企業の日本鉱業と中企業の小林鉱業とが、いずれも貴重且つ高価なタングステン鉱の採掘を競いあうように稼働していた。そしてそれぞれの鉱山に勤務する内地人社員はいずれも四十名余りだった。 まさに鉱物が採れるから、人の住めないような渓谷にも土木技術を駆使して人の住むための場所をつくり、採掘場、選鉱場、そして社宅がぎっしりとけわしい斜面にへばり着くように密集しているのである。隣の百曹年鉱山も同様だった。しかし私が父の勤務するこの鉱山を訪れて強く印象に残ったのは、このけわしい谷あいの斜面に密集して発展した鉱山衆落そのものよりも、二つの鉱山の下流二キロメートル余りの間に、渓流に沿って発達した所謂「砂鉱採り」聚落だった。 この鉱山を訪れるためには、京城から平壌方面に向かう京義本線の列車で三時間余り、新幕という駅で下車し、そこから鉱山の定期便とも言えるトラックに便乗し約四時間を要した。トラックは黄海道の平野を約百キロメートルぐらい走って谷山の町に達し、更に狼林山系の支脈の低い峠を越えて臨津江の上流に沿って北上し、分水嶺に近い谷間に在る箕州鉱山まで約五十キロメートルの谷あいを上って行くのである。 砂鉱採り聚落は鉱山の手前約二キロメートルぐらいから道路と渓流に沿った狭い場所に細々とそしてエンエンとつながっていた。それらの小屋はみすぼらしい温突と物置兼炊事場のバラック建てが多く、また食用にするためなのか赤犬を飼っている家が多かった。この聚落の人々は谷川の川底から粉末になったタングステン鉱を採取もそれを鉱山に買いとってもらって収入を得ていた。二つの鉱山の選鉱場から洩れて渓流で流され川底に砂金のように沈んでいるタングステン鉱の粉末は評価が高いので、主として農村地帯から採取稼ぎの人々が集まるようになっていた。昭和十四年頃には一千名を越える細長い渓流沿いの町を形成していた。そして二つの鉱山それぞれを貫いて流れ出る渓流の合流点付近には、ややゆとりのある平面があり、聚落の住民を顧客とする食料品店、日用品店、飲食店等が数軒あった。 父の転勤赴任に続いて十月中旬に私は連休を利用してこの鉱山を訪れ二日余り滞在した。鉱山施設の見学を終えての帰り途、私は独りで砂鉱採り聚落を訪れる積りで鉱山区域の出口まで行った。そして棍棒を持って警備している会社直属の警備員に自己紹介をしたうえでこの聚落に出かける了解を得た。警備員は二人居たが共に二十五,六歳の日本語の上手な青年だった。 私は警備員の話を聞きながら、少し離れた下流にある小屋の屋並みを見やっていた。聚落の中を歩き廻っている赤犬の姿や吠え声もあちこちから聞こえた。子供たちは粗末なチマとチョゴリを着て、トラックの通行も少ない道路の上で遊んでいた。 渓谷は秋もたけなわだった。谷の斜面の紅葉が美しかった。比較的岩の多い渓谷なので紅葉と岩とが一体となって、青空と午後の陽射しに色鮮かに照り映えていた。私は一軒の一杯飲み屋を兼ねた店に入って「焼餃子」を注文した。店の若い娘が私を見て、 粗末なテーブルの上の牛乳瓶に桔梗の花が二本萎れかかっていた。他に客は居なかった。 谷川の流れの音が絶えず聞こえていた。聞こえているというよりも渓流の音の中に砂鉱採り聚落がすっぽりとつつまれていると言った方が実感だった。 その花を見つめながら私が「トラジ(桔梗)トラジ トラージ シーム シーム サンチョーネ ペクトラジー…」と低い声で口ずさむと、店の娘は私に声を合わせるように高い声で続けて、 「エーヘイヤ エーヘイヤ エーヘーヤ。 彼女の歌を聞きながら、私は昨年九月に行われた学校教練の濱習場の風景を思い出していた。場所は朝鮮の中央部の平康高原だった。高原には桔梗の花が咲き乱れていた。秋の澄み切った青空、高原のそよ風、薄紫の桔梗の花。更に私の連想は続いた。新幕の駅からトラックでこの鉱山に来る途中の風光、それは狼林山脈の支脈の丘陵地帯だった。道の畔に拡がるすすきの原、そして点在する桔梗。既に十月も中旬なので、桔梗もすすきも枯れ果てて、沿道には人家も少なかった。 このような風光を想い浮かべていたせいか、彼女が「トラジ」を歌い終ったとき、思わず「淋しいなあ」という言葉が私のロから洩れ出た。彼女は自分の歌を感銘深く誉められたものと受けとめたのか、嬉しそうにほほえんだ。山深い谷間には日が陰り、はやばやと冷え込む夕暮れが迫っていた。 「五番坑の坑道からの湧水よ、はじめは少し温くかったからよ、鉱泉でも湧き出したんじゃあねえかと思って喜んだんだ」 五十年配の熟練した削岩技手の高橋さんが、 「男湯と女湯ができたら真中の番台に誰が座る?」 「高橋のおやじが座ったら女湯の方ばかり見てるんじゃねか。おっかあが内地から心配して飛んで来るべ」と四十代らしい採鉱技術社員が言った。部屋の中が笑い声で満ちた。高橋さんは家族を 内地に住まわせて単身赴任だった。鉱山の合同宿舎の夕食後のひとときだった。 私も最初一時間余りその雑談の席の隅で足を伸ばして聞いていたが、八時頃になって父の個人の部屋に戻り温突になっている床に敷かれている布団に横になった。 私の脳裏には「砂鉱採り」聚落のたたずまいがこびりついて離れなかった。あの聚落の人々の飲科水はどこから汲んで来るのか。生活排水はどう処理されているのか。これから冬にかけてのオンドルの燃料の薪は、等々が気になった。伝染病対策を含めた衛生施設はどうなっているのか。 私は関連して、京城の町はずれの処々に自然に形成されている「土幕民」聚落のことが頭に浮かんだ。それは医学部に在学する先輩から仄聞していたのだが、「土幕民」は農村から生活貧困のため離農して都会に入り込んで来た者が大部分を占めていた。住居は殆どが一部屋だけの狭いみすぽらしい小屋に家族ぐるみで居住し、小川の土手や空地に聚落をつくっていた。その光景は郊外地に向かう市内電車からも見受けられたが、昭和十四年には京城附近だけでも四千数百戸に達していた。この状態は社会問題としても見過ごし得ない現象であり、医学部学生を主とする有志が翌年からその実態調査を行うことになっていた。 資本制経済の発展の過程で、生活上の事情から離農者が増加し、都会地や鉱山等に集中する傾向が、軍需産業の発展によって更に顕著になっていることは、日本国家全体としての傾向ではあった。しかしそのひずみの現象の一つとして京城の町はずれの土幕民聚落の増大や山奥の鉱山附近の「砂鉱採り」聚落の形成をまざまざと見つめることのできた体験は、私にとって社会問題への関心をそそる大きな収穫だった。 箕州鉱山からの帰途も会社のトラック便に便乗した。そして京義本線の新幕駅でトラックを降り、この駅始発の各駅停車の列車で京城に向かった。幸いに席はとれたが殆ど満席だった。 しばらくして土城という駅に着いた。この駅は黄海道の道庁の所在地である海州や白川温泉への乗換駅である。下車する人も多かったが通路に立って居た人たちで殆ど満席になった。ここから乗り込んで来た多くの人々の中には内地人もかなりいるようだった。その中に五十歳前後の二人連れの内地人の男性があった。昼食時に酒を飲んだのか未だ酔いの残った荒々しい顔つきで通路に立って大声で何か語り合っていた。しばらくするとその中の一人がどなるような調子で、 「おい誰か俺たちに席を空けてくれんか」と言ってあたりを見廻した。近くの席の乗客は皆朝鮮人だった。誰もすぐには席を譲ろうとはしなかった。「誰か席を空けろ」と男は周囲を睨みまわしながら繰り返した。 やがて私の立っている横の席の朝鮮の青年が二人立ち上がった。 私は私の横で道路に並んで立ったその青年たちにたいしてすかさず「コマスミニダ。ありがとう」と言った。青年たちはその男たちと無関係な私が礼を言ったのでけげんな表情だったが黙ってうなずいた。 すると酔って赤い頻の男たちの一人が、私をにらんで、 すると男の一人が、「内鮮一体と言って朝鮮人を甘やかすから…」と言いかけた。もう一人の男はその言葉を遮るように私に向かって、 「お若い学生さんよ。朝鮮は平和だよ、俺たちはな、満州の奥地の松花江のかみの方の発電所の工事現場で仕事をしてるんだ。匪賊が時々弾を撃ち込んで来るんだ。沢山の中国人を使って工事をしてるんだが、テロをやる便衣隊員も紛れ込んで来るし、現場監督は毎日が生命がけだ」 彼は車中に聞こえるように大声で言った。そして声を落として仲間に語りかけるように、 列車が開城を過ぎた頓には、二人の男はいびきをかきながら寝入っていた。
朝鮮民族は日本が朝鮮全体を領有して以来、その大多数を占める農民の中から、日本自体の資本制経済の発展過程の申で、次第に労働者としての需要を充足する方向に移動する者が増えていた。そして昭和十四年度には移住者とその家族を含めると百万名に近い朝鮮民族が日本内地に生活しており、その大部分が鉱山や工場あるいは土建作業場の労働者及びその家族だった。また特に北朝鮮の鉱山、工場地帯を主とする朝鮮内における朝鮮人労働者も同じ年度で三十万名を越えていた。 私は朝鮮の工業化が日本の大資本の進出と平行して進んでいること、朝鮮農民の離農、そして労働者化を進めていることと相侯って、朝鮮人の社会意識や生活意識にどのような影響を及ぼしているか知りたいと思った。 学友の具本純とは私が大学予科二年生の頃から個人的に親しくつき合うようになっていた。文学的な趣味が親近感を湧き起こしていたのである。 「君の関心に添った問題をテーマにしている小説はいろいろあるよ。例えば韓雪野の、『過渡期』という作品や、李北鳴の、『午前三時』という作品なんかは、どれも日本窒素の興南工場の建設や労働者を素材とした作品でかなり評価されている作品だ。しかしこのような作品を読もうと思ったら朝鮮語が読めなければ無理だ。現代の朝鮮の作家は高等普通学校(旧制中学校)を出て日本の大学で勉強した人が多いからみんな日本語は達者だし日本語の文章力もあるんだよ。しかし作家たちの多くは朝鮮ではみんな民族語で小説を書いてる。何と言っても民族のこころは民族語でなければよく表現できないからなあ」 具本純の説明はもっともなことだと思った。彼はなお言葉を付け加えて、 私も同感だった。朝鮮が日本の領土であり朝鮮民族が日本国民となっていても、やはり内地人はもっと朝鮮をよく理解しようと努力すべきであり、そのためには内地人はもっと朝鮮語を覚えなければならないと思った。 総督府の言語政策は朝鮮民族全体には日本語を普及することだった。その政策は朝鮮民族を皇民化するという基本的な政策路線の遂行のために年を追って強化されていた。それでも未だ昭和十四年の初め頃は朝鮮人の小学校では任意科目として朝鮮語が授業科目の中に残されていた。したがって総督府編さんの、朝鮮語を学習するための教科書の一年遅れのものを書店で購入し、自分なりに正規に朝鮮語を学ぼうと心がけた。 学ぼうと心がけると先ず初級程度ならば学友はもとより、家政婦として自宅に雇われている女性も良い家庭教師だった。私の家の家政婦は結婚歴のある三十歳を過ぎたばかりの朝鮮の女性であり、日本語も堪能で炊事にもよく馴れていた。母は彼女を相応に待遇したし、彼女はわが家の家族の一員のようにうちとけて働いてくれた。 具本純は映画や文芸の方面に趣味が広く造詣が深かった。私は彼から朝鮮のこの面での知識をおおいに啓発された。当時朝鮮の文壇で活躍していた文人の一人に金文輯という作家がいた。彼は作家としてよりも評論家として特徴があった。彼は内地に渡って旧制松山高校から東大の文学部で学び、日本語にも熟達していて日本の著名な作家ともつながりを持って活動していた。彼は朝鮮語による朝鮮文学の樹立を主張していたが、その主張の展開において、朝鮮の近代的な文学の民族語での実現が困難ならば、民族語によらず日本語で朝鮮文学の近代化を樹立すればよいではないかとの見解を発表していた。 具本純は金文輯氏に個人的に知己を得ていたので、私は彼に諮って一度金文輯氏に話を聞く会を持とうではないかと提言した。私は予科学生のうちに学生としての自由の立場で少しでも朝鮮の知名人に触れておきたかった。同好の友人たち八名が集まり国文学の近藤時司教授のご好意でお宅の応接間を使用させてもらった。日曜日だったので学校のクラブ集会室は利用できなかったのである。 金文輯の立場は芸術至上主義の傾向とも評されていた。その日の話題は「文芸美について」だった。彼は講話の題材として自分の執筆中の原稿を使った。そして話の途中で指摘した部分を会の世話役である私に声を出して読むように指示した。彼の原稿は日本語を駆使して、緻密な心理描写、繊細な情景描写に富んでいた。検閲のうるさい当時なので印刷された場合には伏字になるような内容も含まれた原稿だった。それをそのまま読まされることになった。女性の局部のへヤーは恥毛という用語で表現されておりモーパッサンの『女の一生』やアルツィバーシェフの『サーニン』のような名作の翻訳の場合でも○○とか××とかで伏せられている図書でしか読む機会のない私にとって、声に出して読むのをついためらってしまうような性的描写の部分があった。そのようなときは彼は微笑しながらその部分を自分で読んでくれた。彼のように日本語が堪能ならば、朝鮮の近代文学の国際的評価を高めるために敢えて民族語にこだわらなくとも良いという彼の見解が理解できるような気がした。大学の先輩でもあり学者として教壇にも立っていた兪鎮午教授は民族語による著名な作家でもあった。次の機会には兪鎮午教授に話を聞くことを具本純と語り合っていた。しかし実現しないうちに予科生活が終わりに近づいてしまった。 朝鮮民族に対する総督府の日本語使用の政策は次第に強められていた。その政策は朝鮮語を民族語として認めながら日本語の普及を計るのではなく、朝鮮語の使用を制限し否認しつつ日本語の使用を強要しようとする方向に進んでいた。金文輯氏のような見解はその政策に活用される可能性があった。十月中旬には朝鮮文人協会が結成された。金文輯氏もその幹部の一人だった。協会は内地人、朝鮮人の、朝鮮文壇で第一線で活動している主な人々をメンバーとして構成されていた。協会結成の趣意には、朝鮮の文壇のメンバーが協力して日本文化の進展に貢献するとともに、朝鮮民族の文人たちも民族語によらず日本語で文筆活動をすることが含まれていた。 私は具本純と連れだってこの会の結成記念講演会を傍聴した。会場は京城の中心街である光化門通りの府民館だった。千名余りの席数の八〇%が聴衆で埋まっていた。そして協会の幹部となっている文人たちの挨拶があり、講演や作品の朗読等が次々に披露された。朝鮮の文人の代表として、民族作家としても人柄としても大きな信望を受けている「李光洙」をはじめとして「李石薫」、「朴英煕」等の著名作家が日本語で力の篭った講演をしたことを記憶している。日本の在鮮の文人は京城帝大教授の辛島驍。京城日報文芸部長の寺田瑛、緑旗連盟主幹津田剛、帝大予科教授杉本長男たちだったと思う。日本語による文芸活動を通じて大東亜の文化の発展に寄与するという文人協会の立場は、日本の東アジアの文化的指導国家としての活動の一翼と期待されていたし、朝鮮の文人と内地人の在鮮文人が共に日本国民としての意識を強め貢献度を高めるために協力することは当時としては国策として要請されていることでもあった。講演者の一人一人は演壇に立って熱情の溢れる講演をした。しかし会場の雰囲気にはあまり盛り上がりが感じられなかった。私は講演者の言葉をそのまま信じることができなかった。むしろその言葉に秘められている真意がほかにあるような気がし、それを汲み取ろうと心がけた。辛島教授や李光洙のような著名な文化人が時局柄とはいえどの程度まで自分の言葉に責任を持ち自分の本当の見解を述べているのか探りを入れる想いで聴いていた。このような気持ちで聴いていると、いつの間にか「朝鮮文人協会記念講演会」という文化人を俳優とするテーマの芝居を鑑賞しているような心持ちになっていた。 李光洙のような朝鮮民族の誇りを担った民族語による作家が、朝鮮語から離れて日本語による作家活動をする決意は彼の本心なんだろうか。あるいは朝鮮民族にたいする日本政府の信頼を高めて朝鮮民族をかばい、民族的立場をぎりぎりのところで擁護しようとしているのではないかとも思った。 また辛島驍教授のような学者が、たとい本人の性格に根ざす行動ではあっても、文人協会という国策に協力する政治的活動に共鳴しその幹部となることによって、彼等指導的朝鮮文人たちの良き協力者となり、間接的には朝鮮民族にたいする政治的圧迫の緩和剤となるという役割を担う積りなのかとも想像した。 朝鮮民族に日本語を常用させるという政策は総督府がいかに努力しても促進することは困難なようだった。民族からその民族の言葉をとりあげて日本語を強制するということは、強制の効果が上がっているように見えても反面民族の反抗心をかきたてるというマイナスの現象も拡がっていた。当時二千数百万名の朝鮮民族が朝鮮半島という民族固有の土地で生活しているのである。日本に朝鮮全土を支配され、民族全部を強制的に日本国民とされているという現実が民族感情として日本語常用の促進をはばんでいた。帝大予科のキャンパスでは休憩時間には朝鮮人学生同志は常に民族語で語り合っていたし、総督府の行政指導をいかに強化しても朝鮮人社会ではやはり民族語が愛用されていた。しかし日本語は公用語として強制されていたので全般的には使用範囲も拡大されていた。朝鮮人にたいする小学校教育、中等教育の普及が進められ、工業化が急速に労働者の需要を増大し、人口の都市集中も顕著になっているので、実用面では日本語の使用は普及が顕著だった。つまり一般に朝鮮人社会における日本語の常用化は民族感情によってはばまれていたが、実用化は政府の政策の浸透と産業、経済の発展によって進展していたのである。 朝鮮文人協会の発足後の李光洙をはじめとする在鮮の主な作家や評論家たちの日本語による活動と平行して、日本内地における作家たちの朝鮮の民族問題に関連する作品も目立ちはじめていた。それは金達寿、金史良、張赫寅、等々の在日朝鮮人作家の日本語による作品であり、また多くはなかったが湯浅克衛、川上喜久子等々の朝鮮で育った内地人作家たちの作品である。これらの作品は日本の一流出版社から単行本で次々に出版され全国的に販売されていた。私はこの人たちの作品をできるだけ読むように心がけた。民族間の感情、それぞれの民族意識、民族交流などにわたって、私は自分の日常体験にも裏付けながらさまざまな作品を味わった。 級友の姜準は休み時間に語る機会が比較的多い朝鮮籍の学生だった。彼が「一度君とゆっくり話がしたい。俺の家へ来てくれんか」と私をさそった。級友であっても自宅にまで訪れることは民族が異なる場合は非常に稀だった。クラスの三十五パーセント余りが朝鮮籍の学生だったが、学校の外で内鮮の学生が相互につき合うことは少なかったのである。具本純は私の家を数回訪れたが、私は彼の家を訪れたことはなかったし誘われることもなかった。彼の言葉の端ばしから察すると、彼の家庭内の事情によるものらしかった。彼の家庭では親や祖父の前では眼鏡をかけることも礼儀を失する行為として禁じられていると語っていた。私は姜準の誘いが嬉しく、お互いの心情の理解を深めるための好い機会と思って早速訪ねることにした。 彼の家は鐘路三丁目あたりから北側に数百メートル入った高台にあった。朝鮮式の塀をめぐらした広い門構えの家だった。温突のある個室が並んでおり、訪問するとその一室である彼の部屋に通された。学友の李在完も先に来て待っていた。話が民族問題に係わって来ると二人はこもごもにいろいろな事実を挙げて、日常的なことがらを初めとして政治的、社会的、経済的な民族差別について私にその認識を深めさせようとする口調で語りはじめた。私はこの問題について自分なりに見解をまとめるよう常々心がけてはいたが、その内容が総督府の行政方針に反する場合、どの程度まで批判が放任されているのか、或いは不穏当な見解を懐く学生として官憲が目をつけるか解らなかった。私は言った。 「民族間題について、朝鮮に住んでいる内地人と、日本内地に住んでいる内地人一般とは考えかたが違うようだし、在鮮の内地人も、朝鮮で生まれあるいは子供のときから朝鮮で育った内地人と、青年になってから朝鮮に移住或いは転勤して来た内地人とでは感じかたが違うように思われる」この私の言葉を受けとめながら姜準が問いかけて来た。 「たしかに個人の事情によって見解が違うと思われるが、君はどう考える?」 私は話がとげとげしくならないように気をつかって説明した。 「君の場合は?」と李在完が聞いた。 「僕の場合は父が会社の転勤で五年余り以前に内地から朝鮮に家族が転居して来た。さっきの例で言えば青年期になってから朝鮮に住むようになった内地人ということになる。僕の民族問題についての考えは今のところ白紙の状態だ。しかし感想の程度で言えば、両民族は近代国家を形成する国民として、相互の民族性の長所、短所を補いながら諸制度の改正を進める方向で差別を解消し、民族問題に合理性ある解決を見出して行くことが必要だと思う」 「そういう考えも解るような気もするが、要するに漸進的改善論の一種じゃあないかな」 「日本は国土としても国民としても、朝鮮の土地および朝鮮民族を切り離すことができないという認識の上に立っている。現在協調されている内鮮一体の政策は、政治上も経済上も民族差別を無くして真の一体を実現する方向に進む以外は無いと言われている」と説明した。 姜準は言った。 神社を礼拝するのは朝鮮民族にとっても道徳として守らなければならないとか。家庭内でも民族語を使わず日本語で話せとか。更に最近では日本式の氏名を名乗るように創氏改名の制度まで推進しようとしているとか。全く、内鮮一体とは朝鮮民族の伝統も矜持も考慮せずにひたすらに大和民族化、皇民化することばかりがその内容になっている」 彼は日頃から胸に溜っていた欝憤を続けざまに内地人の学友である私に投げかけることによってややすっきりした気分になったのだろうか。 「皇民化という言わば思想統制のような政策は、われわれ日本民族にたいしても強化されて来ているよ。美濃部教授の憲法学説が政治的に弾圧され、河合栄治郎教授の思想すら著書が発禁になろうとしている。思想統制がますます厳しくなって来たからな。しかし君たちの苦しみがどんなに深刻かということは今夜の話からもしみじみと理解できるような気がする」と私が言うのを彼はうなずきながら聞いていた。 以前私が本籍の大阪に旅行したとき、中学校の頃からの友人の学生たちと朝鮮問題や民族問題について語り合う機会があった。 友人の一人が言った。 「保護国としてのままだったら、何と言っても一応の独立の形式は保っているんだから、朝鮮民族との関係も民族問題一般も大部質的には異なっていたんじゃあないか」と他の友人が言った。 「しかし既に合併して三十年が過ぎ、政府は朝鮮民族を日本国民として皇民化する方向に進めている。朝鮮民族を、その民族性も民族語も変えて皇民化しようとする現在の内鮮一体の理念は、実にいろいろな矛盾を胎んでいる」 私の説明にたいし友人は更に問いかけて来た。 私は友人のこの言葉を聞きながら、内地では戦時下の今でも朝鮮よりずっと政治的思考の自由があるなと思った。総督行政下の朝鮮では朝鮮人ばかりでなく内地人にも政治的行動の自由がなかった。政治的思考の自由すらも、内地人は自主規制的に国策のわくの中にはまっていることを痛感しないわけにはいかなかった。内鮮一体を論じる場合でもそれは朝鮮における内地人と朝鮮人との一体論であって、全日本人と全朝鮮人の一体論ではないようだった。 「君は朝鮮に住んで日常的に朝鮮人に接しているから、朝鮮人にたいする批判も好意も結局主観的な立場から脱し切れていない。もっと全日本的視野から民族問題を考え、政策にたいする批判を活発にすべきではないのか。 世界の近代国家で、自国の植民地の固有の民族を自国民化しようとしている国はどこにもありはしない。朝鮮民族の皇民化政策なんかは、民族の本質にそぐわない無茶な政策だよ」 内地に住んでいる日本人は各人各様に、他民族との関係について何のこだわりもなく意見を述べている。しかし朝鮮民族のことは自分にかかわりのないこととして他人事のように考えている。私は内地の友人たちに接してひしひしと孤独感に陥らざるを得なかった。 これにたいし朝鮮に住んでいる内地人は、相互にどんなに見解の相違があっても、日常的に朝鮮民族の心に触れ、朝鮮の大地に立っている。朝鮮人の問題は他人ごととして割り切れないしがらみを背負っているのである。 こんなことを断片的に思い出しながら語り合っているうちに八時半近くになっていた。 鐘路通りの繁華街に向かって緩い坂道を歩いて行った。晩秋の夜風が冷たかったが制服のマントを着ているので寒くはなかった。 「戦争になる以前は、鐘路はもっとにぎやかだったし、ネオンサインももっと華やかだったんだがなあ」 私たちは裏通り.の比較的大きなスリチビ(飲屋)に入った。店の中央部の調理場に肉のついた大きな牛の骨がぶら下っていた。カルビー(焼肉)とキムチ(漬物)を食べながらマッカリと日本酒を飲んだ。他にも十数名の客がみんな朝鮮語でにぎやかにしゃべっていた。日本語で話しているのは私たち三人だけだった。 「ここでは、さっきの議論は止めよう」と姜準が言った。 ジエリアン・ディゲィヴェ監督のフランス映画「望郷」と「三人の仲間」が主な話題になった。 更にドイツ映画も、アメリカ映画も。映画の話は学生同志の共通の話題だった。 「今度の予科の文芸誌に具本純の『朝鮮映画史考』と題した論説を載せることになった」 三人とも程々に気分のいい酔い心地になっていた。晩秋の夜気は冷え冷えとしていた。 私どもは私を真中に肩を組みながら、人通りの少ない裏通りを歩いた。 誰かが「頑張れ!」と声をかけてすれ違った。 どのように頑張らなければならないかはっきりとは覚えないまま、私は肩を組み合わせた両腕に力をこめて歌い続けていた。 |