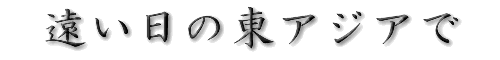
|
第五章 民族の想い
日支の戦争の長期化とともに、日・満・支間の物資輸送、軍需輸送、人々の往来も増加し、朝鮮を経由する鉄道輸送とともに大連港、天津港、上海港等を経由する船舶輸送が大量の物資交流に貢献していた。門司港は大陸との船舶輸送の基地としての役割が大きく、殷賑を極めていた。 五日間の旅程を終えて門司港から連絡船で下関港に戻ったのは午後一時頃だった。私は関釜連絡船の夜行便で釜山に渡り京城に帰る予定だったので、午後の空き時間を長府方面の見物で過ごそうと思った。電車で赤間宮に参詣し、更に町内に入って侍屋敷の町並をそぞろ歩きした。そして忌宮神社から乃木神社へと足を運んだ。神社の境内では、赤ん坊を背負ってあやしながらねんねこを着た十七、八歳の娘がゆっくり散策しており、十歳位の女の子が二人で石けりをして遊んでいた。参拝を終えて後ろを振り向いた私はその子守娘と目が合った。 「この近くで、ほかに何処を見物したらいいでしょうか」私はとっさにこの娘に声をかけた。すると娘はごく自然な様子で、 私は彼女の熱の篭った言葉に引かれて、「行きます。行きます」と二度も答えて、 「どっちへ行けばいいんですか」と聞いた。 彼女は、「私がいっしょに御案内します」と言って、「ひろ子ちゃん」、「きみ子ちゃん」と、近くで遊んでいる少女たちを呼んだ。そして「私、この学生さんとお初さんの墓にお詣りに行きます。あんたたち、ここで遊んでる?」と聞いた。 「わたしも行く」と言ってひろ子と呼ばれた少女は私の方を向いてにっこり笑った。 長府の町並は落ち着いた屋敷町のたたずまいを見せていた。毛利家につながる城下町の長府は、武家時代の伝統を滲ませているとともに明治維新の激動の跡も偲ばせているが、今はやわらかな春の陽射しを町いっぱいに浴びてしずもっていた。 「お兄ちゃんのおうちは何処?」とひろ子ちゃんが並んで歩きながら聞いた。 するときみ子ちゃんと呼ばれた少女も、「わたしの親せきの小母さんも京城に住んでる」と言い、更に続けて、「わたし去年の夏休みにお父さんと京城の親せきのうちに行ったの。そして『いとこ』と遊んだの」 実際に京城には山口県出身の内地人が多かった。二、三年前に新聞社が朝鮮に住んでいる内地人の本籍地調べをし、その結果が発表されたが、山口県が最も多く熊本県、福岡県、鹿児島県等がこれに続いて多かったと記憶している。山口県が内地と朝鮮を結ぶ交通の要衝に当っていることが、地理的条件としてごく尤な理由と考えられるが、それに加えて日本から派遣された初代の韓国統監の伊藤博文が山口県出身だったことにも影響されていると思われた。 お初の墓にお参りして電車通りに出ると、夕方の四時に近かった。下関駅行きの市街電車が来るまで、子守りの娘も二人の少女も私を見送ってくれた。電車が動き出すとみんながさよなら、と言いながら手を振った。私も電車の後尾の窓からみんなが見えなくなるまで手を振っていた。 電車を降りて駅に向かって歩いていると、駅前の広場近くで中年の男の靴磨きに声をかけられた。昼間の見物で靴が汚れていたので、足を磨き台の上に載せた。男は私の旅行鞄を見て、 私は彼が朝鮮の出身であり、働き口を求めて渡日し、何等かの事情で今のような境遇になっているのだと思った。 私は靴磨き代を請求された額の二倍支払った。自分が内地旅行でくつろぐことのできた気分のままに、「彼も朝鮮の郷里でくつろぎたいのだろうな」と同情心の湧くまま磨き代を張り込んだのである。 夕食には少し時間が早かったが、関釜連賂船に乗船するには、できるだけ早くから待合通路に並んだ方が座席の確保には都合が良いので駅前の食堂に入り込んだ。内地での旅の終りの夕食であり、壁に並んだメニューを見ながら、今夜は少し値の張るものを食べようと心積もりして目を馳せた。何ぶん、学生の身分であり、親からの小遣いを節約して積み立てた予算の旅行だったので、四日間のあいだ、旅館の宿泊は二泊だけで、他の二泊は短時間の車中泊にした。そして旅館の食事以外はすべて「トースト」か「カレーライス」ばかりで押し通して来たのである。親子丼はカレーライスより五割位値が高かった。私は親子丼を注文しようとして店員を呼んだ。ところがいざ注文する間際になって、やはり最も値段の安いカレーライスにしてしまった。靴磨きに同情して、磨き代を多く支払った分だけ節約しようとする気持ちになったのである。 その夜の連絡船は、七千トンの大型客船昆崙丸だった。十時の出航である。乗客が非常に多いので三千トンの徳壽丸も増便されることになっていた。 下関港の桟橋の待合通路に並んで三十分、一時問と時間のたつうちに、二千名を超す乗客の列は後尾が見えない程に長々と続いていた。仕事上の任務に抱負を抱いた顔。生活上の苦労が滲み出た顔。民族の別を問わず、男女の別を問わず、職業、年齢の如何を問わず、乗船を待って並んだ一人一人の表情には、それぞれに深い物語りが秘められているような風情だった。私のこころは内地旅行のくつろいだ余韻の世界から、アジア大陸に向かう緊張の雰囲気の中に次第に引き込まれて行った。そして日本国民としての使命感のような想いに胸が引き締まってくるのを覚えた。 内地は大陸に住む日本人にとって、こころのふるさとだった。内地は何処に行っても日本民族の社会であり、水と録に恵まれた伝統の彩り豊かな島国の風土だった。朝鮮では何処に行っても本来的に朝鮮民族の社会であり、日本が領有し、日本国家の構成領域となって内地人の住民が増加していっても、住民の絶対多数は朝鮮民族であり、アジア大陸の一環としての風土だった。そこでの内地人の生活は国力を背景に安定した生活であっても、所詮、異民族にとり囲まれての異邦人だったし、国力による圧迫によって、領有したという日韓合邦の経緯がそのまま底流となって、こころを緩める余裕の感ぜられない複雑な緊張が続いていることを否定できなかった。 朝鮮におけるこのような緊張感は、満州においては本質的にもっと明確な性格の緊張感だった。数十万の日本軍、所謂関東軍の武力を背景に、日本本土の三倍の面積と三千万余の人口を有する満州帝国は、日・鮮・満・漢・蒙の五民族協和の国家とはいうものの、実質的には日本帝国の植民地だった。当時三十万人余りの関東軍は別としても、満州国の公務員、満鉄をはじめとする多くの国策会社の社員、商工業者、開拓農民等々と、約九十万人余りの内地人が満州に居住していた。北部、東部はソ連に西部は外蒙古にと、いずれも日本に対抗意識の強い共産圏に国境を接していた。そして西南部は万里の長城を国境として中華民国に接し、日本の満州における国家的策動を中華民国に対する不法な侵略行為と看做し、蒋介石総統を指導者として、日本にたいし執拗な抵抗を続けていた。即ち昭和十二年七月以来既に四年にわたって戦争状態にある日支事変の戦場に続いているのである。万里の長城を境界線として接する華北地帯は、北京、天津、内蒙古を中心に日本軍が優勢を確保していたが、山西省、河北省、山東省等の山岳地帯や農村地帯は、所謂、点と線の確保にとどまる臨戦地帯だったのである。 しかも満州国内においてすら東部、北部の山岳地帯には、抗日共産ゲリラ部隊が出没していた。満州で生活する九十万人の日本人は、関東軍の勢力を頼りに、満州という広大な地域が、北からのソ連邦の威圧に対する国防上の生命線だという意識を使命感にまで高揚して、暑さ寒さの激しい大陸性気候の風土の中に生活し続けていた。 このような情勢の大陸に向かって、関釜連絡船は下関港を昼便及び夜行便を合わせて連日七千名余りの乗客を運び続けていたのである。 八時三十分頃になると乗船する人々の列が動き始めた。満州に向かう人々、朝鮮内の各地に向かう人々、中華民国に向かう人々、数千名の人々の希望と悲哀と抱負とさまざまな生活色等を表情に歩ませて船客の列は序々に乗船口へと進んで行く。 三等船室に座ると、私の周囲には内地からの満州開拓団の先遣隊と思われる人々が五十名余り座っていた。国民服を着用している中年の男性が多かった。 「どちらから来られたんですか」と私は彼に問いかけた。 「国家のため、ご苦労さまです」と私が言うと、横に座っている団員が、 「とにかく、かなりの広さの土地の地主になれることは本当だ。国が保障してくれてるからな。これだけでも夢見てるようだ」 団員同志の語らいになったので、私は横で黙って聞いていた。そして手洗いに立ったついでに、船室の入口にいた船室整理員の許可を得て、外の空気に触れるため数分間、甲板に出してもらった。混雑防止のためなのか、あるいは防諜上の理由があるのか知らされてなかったが、自由に甲板に出ることは禁じられていた。 春には珍しく月の明るい夜だった。波涛の黒いうねりが、月の光の下で明暗の変化を見せながら、人間には分からない運命の流れを包んで拡がっていた。 夜が明ければ朝鮮の釜山港だ。それから特急列車に六時間乗れば京城に着く。その都市の人口の四分の一に当る二十万余の内地人の一人として自分の日常生活があり、自分の親や弟妹も一緒に住んでいるわが家がある。この地こそ自分のこころの安らぎの場である筈だった。内地の旅を終えて、いま自分の家に帰るところなのに、何故連絡船に乗って大陸に向かうと、心が休まるより緊張感の方が高まって来るのだろうか。内地を旅行して内地の人々と共に内地の風土の中でくつろいだ気分になると、改めて自分が現在住んでいる都市が本来は朝鮮民族の国土であることを反省する気持ちが湧いて来るからなのか。内地人としての自分が、朝鮮民族の中に入り込んで朝鮮の都市の住民となることを改めて意識するからなのか。 外の空気を吸って階段を下り三等船室に戻ると十一時頃だった。開拓団の人々は未だ起きて座って雑談していた。 風が出たのか、波のうねりが大きくなったのか、船が大きく黙々と揺れ始めているようだった。 「もう玄界灘だ」と日本人らしい老人のひとりごとが聞こえた。
木村先生は当時四十歳で未だ独身だった。総督府鉄道局の職員にたいする精神面での教養指導を担当して居られた。京城駅に近い南大門通りの裏町の借家住いだったが、階下三間を私塾方式で法華経の研究と教宣活動の場としておられた。毎週木曜日の夜、学習会が開かれ、また別の日を選んで学生会員のために基礎学習として当面は倫理学者、西晋一郎の「実践哲学概論」の輪読会を義務づけていた。大学の法文学部の法学科に在学していた私は学友藤田の誘いでこの会に出席していたが、同じ誘いで学友の大林、吉田、江上も参加し、医学部の真鍋、有光も参加していた。二階の一間には五十年配の朝鮮人の宗教家一家三名(夫婦と娘)が間借りしておられた。草野水雲と創氏改名し、以前は熱心なクリスチャンだったが木村隆義民の指導によって法華経に帰依された方だった。日本語には会話も記述も非常に熟達しておられた。 私は草野氏が何故キリスト教を離れて法華経の信者になられたのか、その経緯を知りたかった。何と言っても当時、朝鮮民族間における宗教活動では、キリスト教系の活動が全般に行きわたっていたし、内地人の優れた方々も、例えば級友の父、秋月牧師のような方が教宣活動に熱意の篭る努力を続けておられた。 その日の午後は草野氏が一人で留守居をしておられ、木村先生は地方へ出張中だった。私はこの機会にと思って、草野氏の信仰上の体験や内鮮一体問題に関する忌憚の無い意見を聞きたいと願った。 「内鮮一体ということは朝鮮人のみに強制する片務契約的な履行行為であってはなりません。内地人は朝鮮人を、朝鮮人は内地人を自分の身体の半分と思わなければ一体とはなり得ません。内地人は一般にその脳裏に焼きついている狭隘な優越感から脱却しなければなりません」 草野氏の言葉は明確で、その内容は内地人 − 日本人にたいして厳しい批判を含んでいた。草野氏は更に言葉を続けて、 日本による併合領有は両国間の国際関係の成り行き上の勢いだったとしても、合併後、日本は朝鮮人に対し、文を専ぶ民族としてもっと人間として尊重する民族政策を採ることが必要だったと思います。幸い天皇の詔勅で朝鮮民族にたいし『一視同仁』の姿勢が示されています。今からでも遅くはありません。天皇の『一視同仁』のお言葉を再確認し強調し、できるだけ政策面にも反映するように配慮すべきだと思います」 草野氏の説明は正確な日本語で内容も整然とまとめられていた。草野氏は自分の過去の経歴をあまり語らなかったが、言葉の端々に覗く漢籍の知識も広く、哲学的宗教的思索も深かったので、かなりの人物だろうとわれわれは想像していた。毎週木曜日の夜に開かれる学習会にも必ず出席され.て居たが、殆ど発言されず、われわれの討論を終始微笑をたたえながら聞いておられた。 草野氏の話が終わる頃医学部の真鍋と有光とがやって来た。 それを継いで真鍋は、 と言いながら、黙ってわれわれの意見を聞いて居た草野氏の顔を見つめた。草野氏は、 何時の間にか大林もやって来て座っていた。そして言った。 一九一九年の七月に、東京帝大教授の吉野作造は総督府による朝鮮支配政策に批判的な見解を雑誌に発表した。「朝鮮民族の同化は不可能であり、民族問題の解決は、民族自治を承認するより外ない」という主旨だった。この見解は、朝鮮の民族主義者に大きな影響を与え、日本帝国内における民族の自治の要求となり国内での政治的地位の向上の主張ともなった。また東洋経済主幹の石橋湛山はやはり三・一運動後の同じ頃、「朝鮮民族との連帯を深めるためには、朝鮮民族に自治を与えるはかはない。日本は朝鮮民族に自治を認めても経済的な打撃なしに活動することは可能である」という見解を発表しており、また東京帝大の矢内原忠雄教授は一層具体的に、法制、習慣、言語等朝鮮民族の伝統を尊重すべきであり、朝鮮には朝鮮の議会を開設して朝鮮の内政は朝鮮人の手で行うようにすべきであるとの見解を出していた。 京城帝大の「尾高朝雄教授の『国家構造論』には、国家の範囲と民族の範囲とは必ずしも一致しない。……一国家が数民族から成り、或いは一民族が数国家に分属することはむしろ国家構成の常態と見られる。……民族自決主義による小国家の簇立という傾向もあれば、国家の領土範囲を同一民族の上に拡大しようという主張もある」と述べられてあり、大学での「法哲学」の講義においても国家と国民に関して同様の内容が語られていた。藤田が最後に討論に加わった。 「尾高教授は国家と民族とについて事実を整理して説明しているだけで、両民族の関係がどうあるべきかなどについては語っていない。日本や満州国のように複数民族が同一国民としてまとまるためにはどうすればよいか。多民族国家であるアメリカ合衆国のような自由経済を基本とした民主主義的統一方式もあればソ連邦のような計画経済を基本とした労働者の連帯による統一方式もある。木村隆義先生は法華一乗の妙法思想によって、日本と朝鮮の両民族が同一国民としてまとまる原理を生み出すことができると信じて居られる」 「宗教上、両民族が共に信仰することのできる普遍性ある原理を生み出すことが可能か。もし可能であるとしてもその原理をどうやって両民族に浸透させて行くのか」 何故このように朝鮮民族にたいし皇民化が可能である旨の期待をもつことができるのか。このことについては、政策論は別として、その理論的根拠とされているものは、東京帝大の喜田貞吉教授の「日鮮民族同原論」だと言われていた。この論説に基づいて日本民族と朝鮮民族の一体性が主張され、朝鮮民族の独自牲を否定する結果になっていた。 私はこのことで予科三年の秋の日に級友の三島と語り合ったことを思い出した。二人とも健康を害して教練を見学していた。見学者は戦闘教練の仮装敵として幕的を並べて校舎裏の離れた丘の上に待横していた。そして待機中の語らいはいつしか内鮮一体論の批判になっていた。私は言った。 「定年で去年大学を去られた泉哲教授が十年余り以前に「外交時報」に書かれた論説を従兄の書斎で読んだんだが、先生はかねてからの持論をこの雑誌で更に強調され、「朝鮮にたいしては完全な自治制度を施くことが必要である旨が説かれている。これは特にイギリスの植民地政策の変化にもとづいて持論を深めたもののようだ。この論説が掲載された雑誌はその後発売禁止の措置がとられている。」三島はうなずきながら、「朝鮮民族に自治を認めることの必要な見解を公けに発表されたのは、泉先生の昭和六年の論説が最後じゃあなかったかな」 近くに居た他のクラスの朝鮮籍の見学者が私たちの話に入ってきた。そして、「現在の日本の同化政策は朝鮮民族の皇民化を、制度上から、言語上からそして日常生活面において強制的に推進する方向まで進めて来てしまっている。これは国家の力による一方的な皇民化の推進であって、朝鮮民族に納得させながらの推進ではない。今では民族自治論に基づく考え方を日本がすることなど全く仮定すらできない情況だ。」ととげとげしい口調で語った。 三島は考え込みながら、「ともかく内鮮問題を民族問題として国策路線をはずれて論ずることは、思考の自由はあっても発表の自由は無い時勢だからなあ」と声をひそめて言った。 所謂日本精神を思想的に解明し、あるいは宗教上の教義を通じて普遍性ある信仰にまで到達するようにとの目的をもって活動している団体は当時京城においてだけでも幾つもあったが、特に内鮮一体についてもこれを思想面、生活面から推進する目的を掲げて活動している団体としてその組織、規模、活動状況において「緑旗連盟」が目立った存在になっていた。その学生部門では積極的に活動している学友もあった。日本精神とか日本民族の特質について、理念の面から解明し或いは世界観としての信念を形成したいとの欲求は、国際関係の緊迫を背景に当時のわが国の学生にも広がった傾向ではあった。しかしこの問題を実践活動を通じて達成しようとする学生は少なかった。朝鮮の学友の中にも一時的にこの路線を進んだ者があったようだったがそれは稀だった。むしろ一般的には民族主義の立場から朝鮮の独立を目指している者が少なからず居り、中には地下活動に入り退学した者もいたし、上級生の朝鮮人学生にはれっきとした共産主義者として秘密裏に活動している者もあると聞いていた。 出張から帰られた木村隆義師は、内鮮一体に関する学生会員の議論の報告を聞かれて、 この頃には、明治時代の社会主義者幸徳秋水のように、日本人で朝鮮の植民地の解放を正面から主張し、日本の植民地支配に正面から反対し続けている人は見られないようだった。そのような情勢下であっても、朝鮮芸術の独創的な美しさ、朝鮮民族の芸術的才能をたたえて、人道主義的立場から日本の朝鮮支配を批判した柳宗悦の見解は、国民一般から高い評価を得ていた。また大正末期から昭和初期の頃には、総督府統治下の朝鮮農民の姿を書いた中西伊之助の「赫土に芽ぐむもの」や独立運動に挺身する朝鮮人の姿をとらえた槙村浩の『間島パルチザンの歌』のような抵抗文学作品が発表されていたが、それらを読むことは困難な時勢になっていた。
|