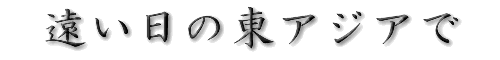
|
第七章 明日を知らずに
九月下旬の日曜日に、町会毎にモデル地区を指定して隣組の防空演習が行われた。民間の防空演習は防空法が制定された昭和十四年以来、次第に実施されるようにはなっていたが、それでも昭和十六年に入ってからは未だ三度目だった。防火用の用水桶、砂袋や火叩き、バケツ等は各世帯に備え付けられ、非常の場合の準備が行きわたっていた。しかしそれらを使用しての訓練は未だ殆ど行われていなかった。戦争の長期化とは云っても未だゆとりあるムードを保ち、朝鮮民族にたいして日本の国力を示すために、あまり切迫感のある防空演習は行わなかったのかも知れない。 日支事変の主戦場は主として中国の山西省、河南省、湖南省方面だったので、戦場は遠く、制空権は広い地域にわたって日本軍の制圧下に在った。したがって爆撃機が飛来する恐れもなかった。 ソ連邦とは中立条約が結ばれているし、ソ満国境地帯には既に関東軍が増強されて配置されていた。朝鮮半島地域は防空上では安全圏に置かれていたとも考えられる。 しかし日米交渉の難行状況、米国の日本にたいする資産凍結、石油の輸出禁止措置等々の緊迫した国際情勢を背景に、総督府は国民にたいして時局の深刻化を強調し始め、防護体制の専門部門も拡充しつつあった。それでも食糧の配給制も未だ朝鮮においてはさし迫った困窮も感じられず、内地人一般には長期戦体制に精神的に馴れ、国力を信顧した落ち着きとも言えるような雰囲気が感じられた。したがって防空演習に参加する隣組の人たちにも、日常生活につながる和やかさとも言えるようなムードが漂っていた。 母が北鮮の鉱山に居る父のもとにしばらく滞在中だったので、各戸から一人ずつ参加する演習には私が参加した。隣組は大和町二丁目の十七番地及び十八番地が連合した総勢三十名余りの、主婦を主とする構成だった。男性は五、六名余りだった。大和町は内地人の世帯が殆ど全部を占めている住宅地帯なので、演習参加者も全部内地人だった。 町会から委嘱された男性の世話役が指導に当り状況想定で演習が始められた。発煙筒を焼夷弾に摸して、道路上五十メートル余りの間に少しずつ間隔を開いて一分置きに煙が上がるように準備された。三十名の消火班は走り廻りながら自然に三こ班に分かれて行動していた。横に並んでバケツリレーをする余裕はなかった。発煙筒に砂をかける者、火炎と想定された場所に水をかける者、水道の蛇口からバケツに水を入れる者、それを三、四人でリレー式に手渡しする人たち。私はいつの問にか消火作業をしながら気がついたことを大きな声で叫んだり呼びかけたり、人手の必要な役割に人を呼び寄せたりしていた。整然とした雑然さで走り廻ったという感じだった。やがて焼夷弾落下の想定訓練は終了した。演習を視察に来た府庁(市役所)の係官も「真剣さが溢れている」という主旨の講評があった。 T子も同じ隣組なので母親に代わって演習にも参加していたが、終ってからもんペ姿のまま器材のあと片づけを手伝っていた。彼女が私の家のバケツを届けに玄関まで来たとき、丁度そこに立っていた私と向き合った。 「しばらくお目にかかりませんでしたね」 T子の父は北鮮の日本海岸の元山港で証券の仲買店を開いていた。彼女は前年三月に女学校を卒業して京城の銀行に勤務したが、母が元山の父のもとに行きっきりになるので、京城の家の方で家事を看る必要があり、一年勤務して退職したのだった。 T子とは近所づき合いで家族ぐるみの知り合いだった。彼女が女学生の頃は小説の話をしたり、詩歌の批評をし合ったりしていたが、私が大学で法律を専攻し始めると話題が疎遠になっていた。お互いに好意を懐いているものの、愛情が燃え上るきっかけもない、しかし会うと話が尽きないというような間柄が続いていた。 「今日の防空演習で、普段おとなしいと思っていた卯一さんが、あんなに大きな声を出して活動なさるとは、見直しましたわ」 「実際に京城が爆撃される日があるのかしら」 「そうなったら日本は相手国に勝つ見込みがたたなくなると思いますよ。だから絶対にそうならないように、外交や戦略に慎重な対策がとられていなければね」 日米交渉は進展が見られないまま六カ月以上も過ぎていた。日本も米国も交渉の決裂を覚悟しているような姿勢をとり続け、双方の主張を緩めようとはしていなかった。 日米の衝突を避けることに関心の強かった第三次近衛内閣は更迭し、十月十八日東条内閣が成立した。 ヨーロッパ戦線では、夏期には攻勢だったドイツ軍のソ連進攻作戦も、ソ連軍のねばり強い抵抗に遭って、スターリングラードの戦線で膠着状態が生じ始めていた。この頃の日本の戦況は、陸軍は満州をはじめ北支、中支、南支の中国戦線を含めて百万名余りに達する部隊が常駐を続けるような体制で配置されており、別に秘密裏に二十万名余りの部隊が、新たな作戦に備えて準備されていた。そして世界三大海軍国の一つとしての海軍は、完全な姿で出動体制がとられていた。 更に陸海軍所属の空軍は、東アジア大陸から中部太平洋にわたって制空権を確保していた。 このように昭和十六年十月の段階としてはかなりに優勢な軍の体制がとられていた。しかし石油の輸入が封鎖されているので、ストックの状態から推測した場合、軍需を主とし最小限の民需をも考慮すれば、あと二年余りで枯渇することは明らかだった。更に食糧始め各種の生活必需物資は、軍需の著しい増強をまかなうため、この年度の後半から急激に統制が強化されていった。
突然、二人の男子小学生が、 言責の抑揚から、その小学生たちは朝鮮人の小学生(当時昭和十六年度から国民学校に制度が変わった)であることがすぐ分かった。 「神社に拝礼いたしましょう」と書いた紙片から目を離して、私は小学生たちの顔を見つめた。利発そうな眼をした真面目な態度の国民学校の上級学年の生徒たちらしかった。 「すみません」と私は彼らに答えて、神社の鳥居の方に向かって敬礼した。 昭和通りから南山の山裾に少し入った所に京城神社の最初の鳥居があり、神社の境内はそこからさらに百メートル余り上った場所が入口だった。其処までの問は両側が官舎を主とする住宅街だった。距離が離れているので私たち内地人は昭和通りを歩いている際には神社のある方向に向いて拝礼することは通常なかったのである。しかし鳥居が見えていれば、どんなに神社の境内から離れていても拝礼することが不適切だということはないし、小学生から注意されれば、「普段、この場所では拝礼しませんよ」と言訳を言うのは、内地人の大人の態度として望ましくないことだった。朝鮮人の生徒が学ぶ国民学校には内地人の教員も朝鮮人の教員もいた。学校として、生徒たちに皇民化教育の方法として神社拝礼の促進活動をさせ、場合によっては私が今日体験したように、神社拝礼について内地人の通行人にたいしても注意を行わせ、朝鮮の少年に日本人としての意識を高める ようにしようとの目的もあるようだった。 京日ニュース劇場の前まで来ると金清昌君に出会った。彼は私の叔父の経営する電気器具販売店 で一昨年まで働いていたのでよく知り合っていた。 「今、どうしているの」と聞くと、 創氏改名の制度が朝鮮民族にたいして施行されたのは、前年の昭和十五年二月だった。初めは表向き創氏改名を朝鮮民族に押しつけるのではなく、朝鮮式の姓名を日本式の姓名に変更を希望するものにたいしてはこれを認めるという主旨で発足する形が採られ、政策的にはむしろ民族懐柔策のようにも感じられた。 朝鮮の「族譜」制度は非常にわかりにくい内容だったが、折に触れて級友からも説明を聞くことがあった。クラスでの席も近かったので、予科の学生の頃は普段から私は朝鮮の慣習や政策的諸制度の説明を朱宰黄君から聞くことが多かった。特にこの族譜制度については、創氏改名の政策が施行された予科を修了する頃、彼から詳しくわかり易く解説してもらっていたので、これが朝鮮民族にとって容易なことではない事情をかなり理解していた。族譜を重んずる朝鮮民族にとってこれが各家族の自由意志のみによるものならばまだしも、皇民化政策の一環として南家的に強制する気配が見えて来たとき、皇民化の方向をやむを得ないと妥協する者でさえ、先祖にたいする尊崇の念を否定する政策として深い感情的反感を生み出す結果となっていた。しかし総督府としては各種の実質的な効果の上がる方策をとって、朝鮮民族全体にこれを押し進めようとしていた。 例えば、朝鮮全体で十三名の道知事が置かれており、そのうち五名は朝鮮人から任命されていた。創氏改名は自分の自由意志によることになっているからと、施行後一年たってもこれを実行しない知事二名は遂に辞任せざるを得ない結果となってしまわれたようだった。 このようにして、金という姓を金山や金川に変更したり李という姓を李家と変更したりして次第に改姓者は増加していった。しかし昭和十六年の夏が過ぎた頃になっても、大学の朝鮮の学友たちで改姓した者は誰も居なかったと記憶している。 大軍を海外に常駐させている事情から、軍部特に陸軍では兵員に不足が生じ始めていた。また軍需工場の労務者、石炭の増産を推進するための労務者の不足が顕著になり、その充足が緊急の問題となっていた。朝鮮人の労務者による内地への充足が、これまでの任意応募だけでは足らず、強制連行を含めた傾向を帯び始めたのはこの頃(昭和十六年十月)からであった。そして軍の兵員充足のため、朝鮮民族にたいする志願兵制度が拡充され、最初の数年は任意志願だったが、兵員増加の要請から志願兵の募集にも強制割当がとられ始めたのもこの頃からだったと聞いている。 日本国民(内地人)は二十歳に達すると帝国憲法に基づく兵役の義務があり、徴兵検査に合格すると軍務に服することになっていた。そして大学や高専に在学する学生は、卒業までは兵役の義務に服することの延期が認められていた。 それが十月十六日付で、大学生も早く軍務に服させるようにするため六カ月繰り上げて卒業さすことが決定された。 即ち文科系の大学の場合三カ年の在学年限が臨時措置として六カ月短縮されて二カ年半となり、徴兵延期年齢を短縮されることになった。即ち当時の旧制学校制度では基準学令で言うと、小学校入学から十四年目の二十歳で大学に入学し、二十三歳の三月に卒業することになっていた。それが六カ月早く卒業となるので二十二歳の九月卒業というように繰上げて卒業することになったのである。 更に引き続いて翌年九月に卒業見込みとなった者にたいしては、事前に四月になると徴兵検査が施行され、その合格者は十月一日に陸軍に入営することが決定された。 また十一月上旬には、六カ月繰上げ卒業との関連で大学の二年次の年度末試験は十二月上旬に繰上げ施行され、第三年次の授業は一月から開始されるとともに、九月上旬に試験が行われ、九月二十日に卒業することになった。 独ソ戦の形勢がドイツ側に不利に傾き始めていることもあり、国際情勢は日本にとって秋の深まりとともに急速に緊迫感を加えて来た。日米交渉は、日本の経済的弱点を握った米国が、強硬な条件を主張し続けていた。戦時措置としての在学年限の短縮に始まった学園生活の緊張は、目の前にさし迫って来た軍隊生活や戦争が、個人の人生設計に不安定要素を拡大しおおいかぶさって来たような想いが伴っていた。 十一月二十六日に米国側から日本側代表に手交された所謂ハル・ノートと言われる文書は、アメリカ例の要求の当初の内容が再び強調されたものだった。それは、(一)中国および仏印からの日本の陸海空軍および警察の全面撤退、(二)日華近接特殊緊密関係の放棄、(三)三国同盟の死文化、(四)中国における垂慶政権以外の一切の政権の否認、という要求だった。それはこの要求を日本側が呑むか呑まないかの強圧要求であり、既に以前から発動されていた石油をはじめとする経済封鎖の実効は次第に顕著になり、日本の国家も国民も重苦しい雰囲気に包まれていた。 「あんた方内地人学生はたいへんだなあ。来年九月に大学を卒業したらすぐ軍隊に入ることになるのか。俺たち朝鮮民族の学生は何と言っても兵役の義務がないから、就職後の待遇には不満があるけど、軍隊と直接かかわりがないだけ気分にゆとりをもてるよな」 この年には未だ朝鮮民族には徴兵制が施行されていなかった。 私の家に立ち寄り書斎で話し込んでいるとき具本純はしみじみと私にこう語った。 「来年軍隊に入ることになったら、以前君と約束していた、谷崎潤一郎の現代語訳源氏物語全巻を君に贈呈するよ」 「そりゃあ嬉しいけど、君も軍隊から戻ったら、こういう本をゆっくり読める日も来るよ」 「わからないけど、あんまりそういう日が私に戻って来ることは期待できないような気がする。君とこうやって語り合えるのもあと十カ月しかないなあ。君のお蔭で内鮮の民族問題を深く洞察するきっかけを掴んだ気がするよ。しかし戦争がどんなことになっていくのかなあ。この戦争との関係で民族問題もいろいろ変転する可能性があるしな」 「そりゃあ深刻な問題だ。戦争の中でこの問題を、『どうすればいいのか』ということと、『どうなっていくのか』ということとが日常性の中で自分で自分の身を縛っていくような気がする」 「この頃のように情勢が厳しくなって来ると、切実に戦争と自分の生命とを直結して考えざるを得ない心境になってしまうよ」 「日本とアメリカとが戦争しなくてもよいようにならんかなあ。日本軍は中国から引き揚げてもアメリカと戦争しない方がずっと得策だと思うよ」と言った。 私は思いつめたような口調で言った。 具本純は私の言葉を受けてためらい含んだような口調で言った。 具本純の言葉を聞いているうちに、私は自分が無意識のうちに国策に沿った主張に入り込んでいると感じた。それとともに彼の見解には国際関係における日本の立場に客観性ある内容を含んでいると思った。私たちは学生の身分という精神的な自由の世界で、私の狭い書斎の中でうちとけて語り合った。そして終りは映画の話になった。 母が紅茶のお替わりとビスケットを運んで来た。朝鮮映画の「旅路」を話題にしていたときだった。母が立ったまま「主演女優、文芸峯の細やかな表情やしぐさが、とてもすばらしかった」と語ると、具本純は、 「戦争が長引いて検閲が厳しくなっても、このような芸術性の高い作品がつくられて鑑賞できるのは嬉しいですね」と具本純が言うと、母はそれに答えるように、 私は「小林一茶」と題する俳句を中心に一茶の人生そして信濃の風土や農民の生活を描いたこの映画が感銘深く印象に残っていた。そして同じ亀井文夫監督の作品で数年前に見た「上海」という記録映画を通じて戦争の精神的深淵を感じさせられたことを思いだした。 夕方になって具本純を送りがてら本町通りの繁華街を歩き、日韓書房という古本屋で彼と別れた。 もう一軒古本屋をあさろうと「大阪屋号」という店に立ち寄った。そこで立ち読みしていると星雲短歌会でお世話になっている沼沢さんが友人と一緒に入って来られた。沼沢さんは私の一年先輩の人たちが主に受験した昭和十六年度の高等文官試験の合格者の一人だった。彼は行政科に、同行の学生は朝鮮籍の学生で、司法科に合格していた。高文の受験との関係もあり沼沢さんは歌会への出席をしばらく休んでおられたのでお会いできたのは夏以来初めてだった。 私は三越デパートの四階の食堂で、沼沢さんとその友人から高文受験準備体験の一端を聞かせてもらった。「学習を受験科目に集中しようとすればする程他の本も読みたくなるものだ。それを我慢して他の社会的問題等に関心を持ち過ぎないようにしなければ受験準備の時間が不足するよ。合格したので今は読書の内容がよく頭に入る。このところ一年あまり読むのを我慢していた本が幾冊もある。入営まで二カ月しかないから、時間が足らないよなあ」と残念そうに言った。 食堂にはツルチュクと言う名の紅色の甘い飲物があった0話が長くなりツルチュクを再度注文した。 「この飲物は北朝鮮の山岳地帯に自然に生えているツルチュクという潅木の実からつくるんだそぅですね。私は去年の夏、友人の福山君たちと北鮮の赴戦高原に旅行しましたが、この実を見ることはできませんでした」と私が言うと、沼沢さんは思い出したように語った。 「北朝鮮の山岳地帯と言えば金日成のことですがね。卒業して私が勤務する総督府のある方から聞いた話ですが、彼は現在はソ連に保護されているそうですよ。日本軍、および満州国軍による制圧が強くなって、朝鮮や満州の山岳地帯に潜んでいるのが困難になったんですね。 しかし何と言っても彼は二十代の青年時代からパルチザン活動の指導者として日本にたいして抵抗を続けて来たので、独立運動の英雄として信望が高いんですよ」 金日成の名は朝鮮在住の内地人たちも皆よく知っていた。そして彼の指揮するパルチザン部隊が、北朝鮮の山岳地帯で国境警備隊を襲撃したり、鎮圧に来た日本軍をゲリラ戦術で苦戦に陥らしたりしたニュースが物語化する程に広がっていた。昭和六、七年頃で二十歳だった彼は年齢から考えても、伝説的人物の象徴化のような評判だった。 日曜日の夕食時の三越の食堂は、メニューの品目が少なくなってはいるが賑わっていた。私はこれから総督府の官吏としてエリートコースの道を歩む先輩たちの、抱負に満ちた真剣な語らいを横で聞きながら、ツルチュクの甘さを味わっていた。
六時を何分ぐらい過ぎた頃だったろうか。ラジオはアナウンサーの「臨時ニュースを申し上げます」との言葉をくり返し放送した。そして改まった声で次の発表があった。 「十二月八日、午前六時、大本営陸海軍部発表。帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」 それは明確な、そして落ち着いた格調高い発表だった。それは日米交渉の行き詰まりで重苦しい雰囲気に包まれていた国民に、突如雷鳴が轟いたような衝撃を与えた。 私の母はいつものように弁当箱を六個並べて炊きたての御飯をつぎ始めた。そして、「こんな大きな戦争が始まってどうなるのかね」とひとりごとを言うような口調で私を見つめた。私は何も答えられなかった。道のない森を抜け出て動かない青空の見える境野に立ったような気持ちだった。この昭和十六年には、私は京城帝大生。弟は京城鉱専生もう一人の弟は京城中学生、上の妹は京城第一高女生。そして下の妹および末弟は日出小学校生徒だった。みんな弁当を持っての登校だった。父は北朝鮮の鉱山に勤務していた。 大学の年度末試験のさ中だったのでこの日の午前中は「行政法」の試験があった。終って午後帰宅すると「宣戦の詔書」の再放送を聞くことができた。そして夜になって真珠湾攻撃の多大な戦果が発表された。更にこれに加えて日本軍が香港、マレー半島へも続々と進攻中であることが放送された。十日になると、英国極東海軍の重鎮であるプリンスオブウエールズ号およびレバルス号をわが雷撃機が轟沈させたというニュースが入った。そして開戦以来約五カ月余りで、日本は東南アジアの全地域を占領下に置いた。 このような広大な領域に短期間に展開された勝利の戦果は、かねてから国策として掲げられていた大東亜共栄圏建設への理念と夢を実現する確信を、国民に広く浸透させ国家への信頼を高揚させた。そして朝鮮、満州を日本の大陸発展の基地として大盤石の基礎固めを進めることは、従前からの一貫した不動の国策として進められていた。 朝鮮と満州に在住する内地人百六十万余は、その大部分はこの地を第二の故郷としていた。国民全般にとって、米国、英国にたいする今後の戦局の重大さは推測できたけれども、戦争緒戦の数々の戦果は、これからの防衛を主とする戦闘の深刻さをあまり感じさせてはいなかった。 私にももとより国家の発展に期待する夢も湧いていた。しかし九カ月後に迫った入営、そして戦争への出征の可能性がその夢に影を落としていた。それでも自分自身の生死を分かつ地平の彼方に、私は日本の栄光の明日を期待していた。
未来を夢みて生活した大地を、自分の命が現実に何の保障もされないl死の大地としてあきらめながら、遠い島国の祖国に引き揚げて行かなければならなかった。 「何故このまま朝鮮に住んでいることができないの」 朝鮮で生まれ、朝鮮で育った内地人の小学生たちは、その父や母に向かって不思議そうに聞いたそうである。 聞かれた父や母がその子に向かってはっきりとその理由を説明することは辛いことだった。そして命がけで山野を辿り、あるいは貨物列車を乗り継いで引き揚げて行く苦労、そして敗戦の祖国に帰り着いたとしても、歯をくいしばっても絶えなければならない生きて行くための苦労が待ち構えていた。朝鮮、満州からの引揚者は、日本の明治以来の国歩の責めを一身に背負わされて、その苦痛の原因を他に転嫁することなく、口を固く結んで愚痴もこぼさず、海峡を渡り玄海灘を越えて内地に戻って行った。外地在住の内地人にとって内地の土地だけが祖国となったのである。
米・英・蘭との開戦当初の勝利の喜びのままに、国家やその国策に対して信頼感を強めた内地人たちは、たとい戦争が長引いても「石をもて追い出される」ように、みじめな姿で朝鮮から引き揚げなければならない境遇になるとは、誰もが予想のできないことだった。 香港を占領した日本は香港に総督を置いて統治した。父は会社の命令で子会社である太平洋鉱業の役員として出向し、九龍の郊外にある香港鉱山の所長として家族を京城に残して赴任することになった。門司港から汽船に乗船するので京城駅から列車で出発することになった。四月上旬の珍しく晴れわたった空だった。十四時四十分発の釜山行特急「あかつき」は京城駅が始発なので、待合室でもプラットホームでもゆっくり見送りができた。 父は私たち兄弟に語った。 「俺は戦争が終るまで帰れんかも知れん。お母さんを大切にしてくれよ。卯一も次男もそして二、三年もすれば三雄も軍隊に入営することになるな。京城でお母さんと一緒に居れるのは昭子と和子とそして泰敏ぐらいだろうな」 父は遠い南方への出発の意気込みと妻子との別離の情の入り交じった表情で語り続けた。 「京城は今の国際情勢から考えれば安全地帯だ。戦争も終る頃には俺も会社が定年になるだろう。そしたら京城を本拠として自分の技術と経験を生かして独立した仕事をしたい」 出札時刻になった。 T子が小走りで見送りに来た。 たとい未来がどうなろうとも、今日の喜びの中に永遠の幸福を感じた。 駅前の停留所に、公用腕章をつけた兵隊が二人立っていた。その中の一人は志願兵を志した金成佑君だった。 「私はこんど上等兵になりました。名は金田成佑と創氏改名しています」 堅く握り合った掌の力を通して、私は彼にたいする想いを伝え、彼は私にたいする想いを伝えていた。 駅の広場の数箇所に、出征兵士を送る何本もの幟が翻り、日の丸の旗を振りながらの歓送の歌が 青空の下で高らかに斉唱されていた。
|